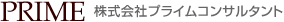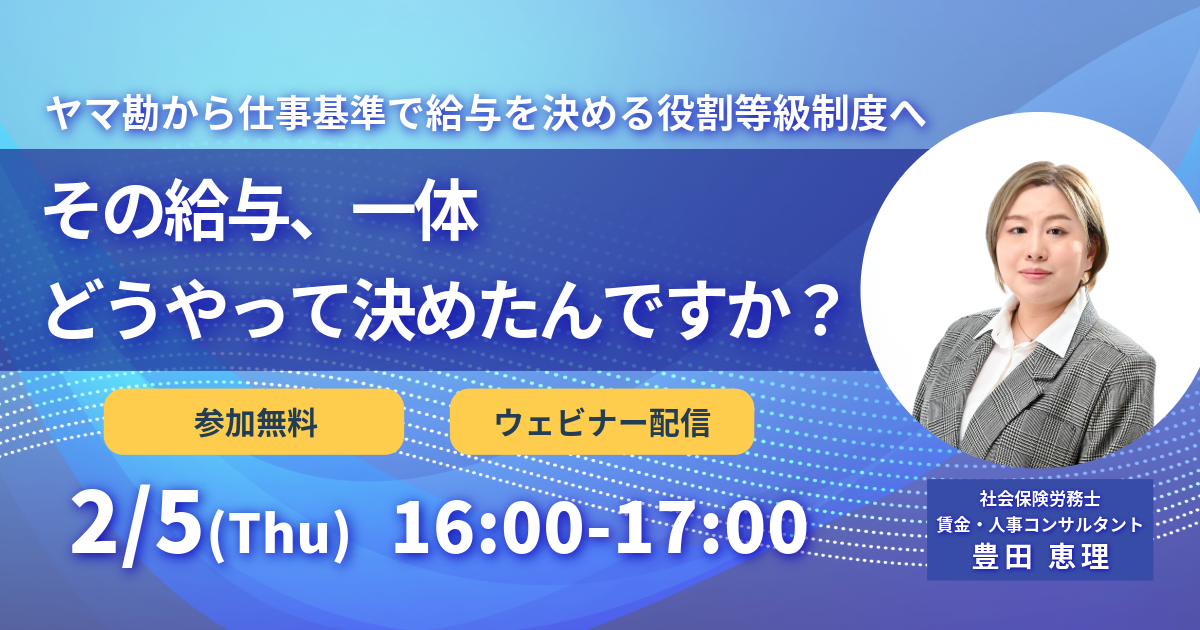たかが100円されど100円(中)(春闘小史・躍動編)

第19回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
日本経済の変曲点
昭和50年(1975年)は、春闘の主役がストライキを前面に闘う国民春闘共闘会議(総評系)から、鉄鋼、造船、自動車、電機などの金属産業を結集した大産別、金属労協(当時で労組加盟組合員の3分の1近い280万人を組織していた)にはっきりと移った年であった。
この昭和50年という年は、日本経済が二ケタ成長から一ケタ成長の中成長に移った変曲点であり、また、オイルショックを境に日本の基幹産業が国際化をしていく変わり目でもあった。というのも、世界経済はオイルショック以前に1971年のドルショックで、ドルの信頼低下という波に洗われており、日本もその波の中で、国際化と呼ばれる変化に突入していく時期にあたっていたからだ。
日本の円は戦後長く1ドル360円であり、輸出競争力を後押ししてきた。しかし、1973年のスミソニアン協定により、日本の円は308円に切り上げられ、1975年頃には250円前後になっていた。こうした中で、世界市場で認められ輸出を伸ばしていた日本の金属産業は、円高による競争力低下という課題に直面し、労働組合としても産業の将来をグローバルに考えざるをえない時代が到来していたのだった。
労働運動の曲がり角
こうした経済的要因に加え、労働運動自体も大きな曲がり角にあった。それまでの右肩上がり経済の昭和30年代から40年代は、労組が盛んにストを打つ「戦う春闘」時代だった。
国民の多くも、いずれ自分たちの賃上げに波及する期待感があり、ストライキに対し、ある程度理解を示していた。しかし70年安保闘争が尻すぼみに終わり、日本国民は次第に保守化する。
決定的だったのは「スト権スト」の敗北だ。昭和50年11月末から12月にかけ、それまで日本の労働運動に大きな影響力を持ってきた国労はスト権奪還を掲げ、8日間のストライキを打ち抜いた。しかし、この「スト権スト」は国民の理解を得ることなく失敗した。
この頃から、国民の間には産別事情を掲げてストライキを打つ労働組合に対する「厭戦気分」が広がっていき、春闘はJCの「ストなし路線」が引っ張ることになる。
この主役交代は、経済学的に分析してみると納得がいく。日本のような貿易立国において、国際競争にさらされていない私鉄や通信部門等の力に頼り、生産性向上の裏付けのない賃上げを行っていくことは、コストの肥大化を招き、国際競争力が低下する恐れがあった。
しかし、国際競争の舞台で戦う金属産業労使が賃上げの相場をリードし、日本全体の賃金水準がそこに収斂していけば、日本の賃金も自ずと国際的視点で決まっていくことになるから、日本経済の健全化に資することになったのである。つまり金属産業が賃上げの中核をなすというのは、いわば必然の道であったとも言える。
JC春闘
金属労協が中心となった春闘は「JC春闘」と呼ばれた。この頃は、3月中旬(この時代、4月第2週に集中回答指定日を配置していた)の春闘中盤に差し掛かると、新聞各社の1面を、「鉄鋼何%、電機はそれをわずかに上回る水準の攻防」というような文句が踊った。
そして終盤に入ると、「新日鉄5.5%前後、電機は5%挟む攻防、トヨタ5.1%確保か」などというように決着予想水準が狭まってくる。そして、最終盤には「日立9800円、トヨタは1万1000円」など、各新聞社は決着額を決め打ちするようになる。世間もそれが、その年の自分たちの賃上げに影響するから、その数字の上がり下がりに注目した。
当の日立やトヨタの職場では、執行部からはそのような具体的な額の報告はないのに、新聞が先に報道するから、「うちの賃上げは新聞社が決めているのか」などという非難の声が上がった。では、このような春闘報道の裏側で、実際にはどのような駆け引きが行われていたのか。

JC春闘の主役たち
そもそも産業が違えば、あるいは同じ産業内でも、年により、企業により、その業績は違う。中には赤字を出す企業もある。しかし日本では、労働組合はほぼ同率を一斉要求し、1%程度の違いはあっても同水準で決着していた。それは、日本の賃金が年功序列であったから可能な戦略であったことは 前回書いた。
しかし一方で、企業サイドでも企業間で大きな賃金差がつくことは、人材確保の面でマイナスになるから、横並びを意識することは合理的だったという事情がある。
また、企業の論理として、鉄鋼メーカーから鉄を買う造船、自動車、電機、また、電機メーカーから部品を買う、自動車、造船というように、相互の取引関係があることから、原価の太宗を占める人件費を産業が横並びで調整して大きな差なく回答することは、競争力の平準化という意味でも意義があった。
そんなもろもろの背景から、前稿で述べた金属主要4産業の中核企業8社(新日鉄、日本鋼管、三菱重工、石川島播磨、日立、東芝、トヨタ、日産)の労務担当は賃上げに関し、互いに連携し、水面下でその水準を牽制、調整する会議や情報交換を盛んにやったのである。
一方の労働組合も、対応するJC8組合の委員長、書記長が狙う水準、そのための物言い、最終局面に向けた歯止めの置き方などについて、頻繁に情報交換していたのだ。
マクロとミクロの賃金決定要素
さて、では当時の春闘において、賃上げ水準はどのようにして決まっていったのか。職場組合員は「マスコミが賃上げ水準を決めている」と怒ったが、もちろんそんなことがあるはずはない(もちろん、マスコミを利用していた面がないではない)。
当時の右肩あがり経済においては、賃上げ水準はマクロ経済要因に規定されつつ、最終的にはミクロの労使交渉の場で決まっていた。もう少し敷衍(ふえん)すると、まず賃上げの大枠がマクロ経済の動静で絞られ、最後の数百円レベルの決着はミクロの労使交渉で決められていたということである。
当時の労働経済学者たちは、賃上げのマクロ三要素として①物価、②労働力需給(失業率や有効求人倍率)、③経済成長率を挙げていた。物価は生計費とリンクするものであり、労働力需給は、人材確保のための横並び意識とリンクする。経済成長率は支払い能力に繋がる企業収益とリンクする。経済学者たちは、毎年秋頃にこれらの数字を睨んで、翌年の賃上げ水準を予測していた。
年功賃金制度の日本では、賃金が横断的に生計費にリンクしていたから、このようなマクロ要因が賃上げの要素となったのは必然だった。労働組合も賃上げ要求を組み立てるとき、当然このマクロ三要素も勘案して決めていた。
要求策定時には、過年度物価と労働力需給がまず要求案のベースとなる。三つめの経済成長要素を「強気」にするか「弱気」にするかであるが、この点がまさにその年の要求水準を決定づける。この部分を労働組合は「向上分」などとも呼んでいた。企業の支払い能力や職場の頑張りを考え、それに見合う数字を見出すのは結構難しい作業だった。
組合員は、自分たちの頑張りが反映した要求水準でなければ納得しない。しかし、要求が高すぎて回答水準との乖離が大きければ、労働組合のリーダーシップが問われる。そういう葛藤の中で、その年の適正な要求案が12月初旬に決められる。労働組合は、毎年この要求案策定のための議論で半年くらいを費やしていた。
躍動していたJC8労使
毎年3月上旬、JC傘下の各組合は一斉に要求を提出した。回答日もJCの大手組合では同日にそろえられた。同じテンポで交渉を詰めていくことも共闘の一つだった。JC8労使は終盤に向け情報交換の頻度を上げていく。
はじめのうちは、マクロの三要素が意識される。しかし、終盤の調整要素は横並びになる。並びつつもそこに企業のポジション、労使の納得性を睨み、組合は少しでも上に頭を出そうとし、会社は自社が目立たないようにそろえようとする。もちろん企業にとって最大の固定費である人件費は増やしたくないこともある。
一方、労働組合は、組合員の生活原資であり経済の成長原資である賃金を少しでも高くしたい。その綱引きは毎年熾烈であった。会社も組合も日に何回も電話で他社と情報交換したものだ。
実際の交渉では、中盤以降、ミクロの各企業内労使交渉で数百円のせめぎあいが行われる。最終盤になると、労働組合は、ミクロの交渉で、たとえ百円でも上に行こうと頑張る。その推進力を支えるのは、労働組合の横の連携(広義の団結力)と、職場をまとめる求心力(狭義の団結力)だ。
JC8労使は、ともに相場のリード役であることを認識し、互いに役割を認め合っていたから、ここでいう広義の団結力は、他の業界に抜きん出ていた。そこで交わされる労使の真剣なせめぎあいが、日本の賃金決定を十数年にわたりリードしていたのである。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。