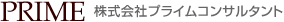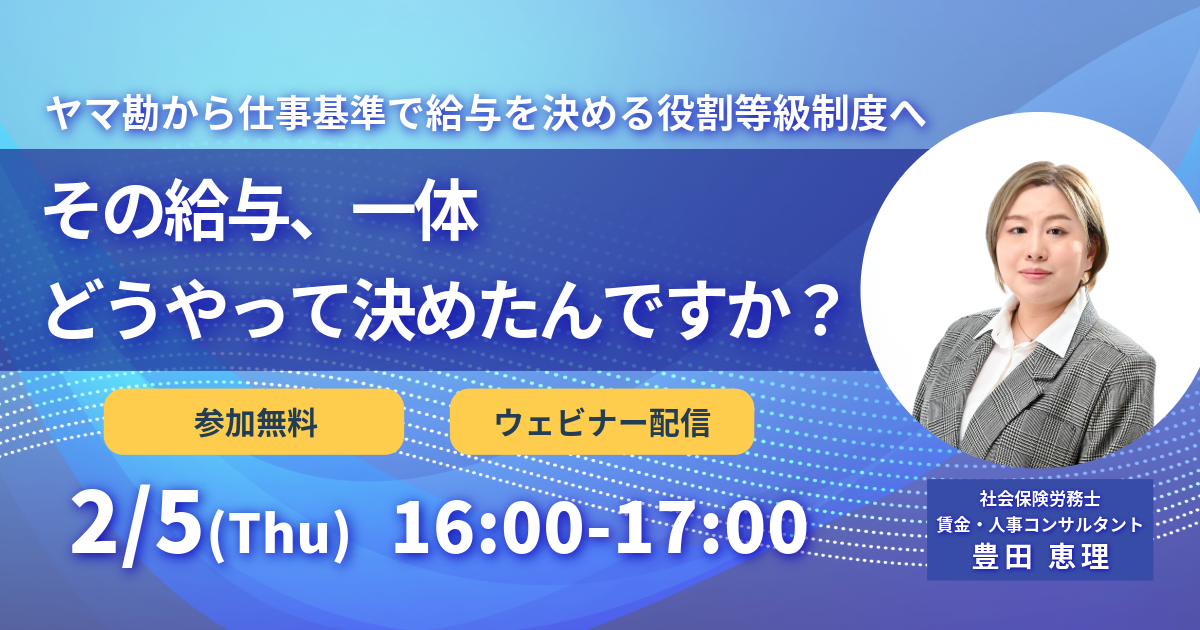夜勤廃止への道のり(下)

第23回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
休日増から残業削減の取り組みへの転換
トヨタ労組は、こと労働時間の取り組みに関しては、本田労組に追いつき追い越せが合言葉であった。なぜかというと、労働時間短縮が労働組合としての大きなテーマに浮上してきた1980年代半ば頃、本田は、すでに年次有給休暇については完全取得していたし、年間休日数も他のメーカー労組に対して一日分先行していた。
それに加えて、年間総労働時間数も自動車総連平均より200時間ほど少なく、突出した「優等生」だったからだ。本田では特に労働時間の取り組みでは、早くから欧州型の運動を志向しており、労組の取り組み姿勢の先進性は他の見本だった。
この労働時間と働き方という面で、トヨタ労組がもう一つ本田に追いつきたかった点は、現業部門の勤務形態であった。トヨタが完全昼夜2交替制をとっていたのに対し、本田は欧米型の連続2交替制(一直は早朝6時から15時まで、二直は15時から24時までの勤務という2交替制)を取っており、夜勤直がなかったのだ。
もとより、人は夜は寝るのが望ましい。一部、夜勤が不可避である業態(溶鉱炉の火を消せない鉄鋼業や、タービンを止められない電力産業など)を除けば、夜勤は避けられるものなら避けるべきだ。
しかし、自動車産業は設備投資が巨大で、これをできるだけフルに活用して効率的に生産するため、昼勤務と夜勤の直間で残業が可能な完全二直の働き方が一般的であった。しかし、労働時間が欧米のように短くなれば、深夜勤務は廃止可能だ。1980年に発表された前川レポートでは、日本の年間総労働時間を1800時間程度に短縮し、ゆとりある生き方を目指すべきとしていた。
日本人の働き過ぎを改める機運を受け、トヨタ労組でも、「いつか、本田のように夜勤のない働き方を実現しよう」という目標が暗黙裡に共有されるようになった。
自動車総連での反対論を乗り越えて
自動車総連では1980年代に労働時間短縮の取り組みが進展し、1992年にはメーカー組合で、年間所定労働時間1960時間、年間休日120日が実現した。120日と言えば休日数で言うと当時122日程度だったアメリカに遜色ない水準だった。問題は残業が多く、年間の総労働時間から年休取得分を差し引き、残業分を足した年間総実労働時間が依然2200時間程度もあったことだ。
トヨタ労組としては、休日増が一段落したということで、総労働時間をせめて1900時間台に持っていくことを目標とし、運動を休日増から残業削減に転換することを決め、自動車総連に対して提言した。
しかし、この運動転換は大きな抵抗に遭った。それは休日増、つまり産業内で休日数を合わせるという理屈は、会社に主張しやすく、「共闘」に馴染むが、残業削減となると、収入減少を嫌がる職場を説得しなければならないし、何より残業削減のためには設備投資、人員の投入が必要となるから、企業体力によってその実現性に差が生じるのが見えていたからだった。
ましてや、数年前に自動車総連共闘で「休日3日増」をもぎ取った成功体験が強く、そのような共闘効果を捨てることに大きな抵抗感があったのだ。
実際のところ、労働組合自身に、企業体力の弱さを残業で補う考え方を乗り越えられない弱さもあった。しかし、労働時間が短いことで競争力が奪われるなら、当時すでに年間1600時間程度だったドイツの企業は、国際競争から脱落していたはずだし、本田も日本で他の企業と対等に戦えなかったはずだ。
残業をするかしないかについては、36協定にハンコをつく労働組合が決定権を持っている。ドイツや本田を見れば明らかなように、労働組合が残業時間をしっかり規制すれば、企業は生産性を上げるために懸命に努力するから企業体質は強くなるはずだ。
トヨタ労組ではそのように考え、粘り強く主張し続けた。自動車総連は3年ほどかけて中央執行委員会や中央委員会、大会で侃々諤々の議論を重ね、ついに1998年、自動車経営者連盟との労使会議の場で、残業削減により産業として総労働時間1900時間台をめざす目標を持つことを合意した。21世紀はもう目前であった。
「本田に続け」を合言葉に残業減を率先垂範
1980年代といえば、日本はバブル経済を謳歌していた。自動車の販売も好調で、販売の引きに製造が追いつかないという時代であった。日本では欧米に比べ所定外労働時間の割増率が格段に低い。欧米は、平日の残業で50%、休日は100%の割り増しが一般的だ。アジア諸国では、一定時間を超えれば、平日でも100%、休日は200%という国が多い。
しかし日本では、割増率が平日で25%と低いから、人を雇うより現有人員で残業する方がずっとコストは安い。したがって残業時間を規制することについて、経営の抵抗は非常に強かった。
さらに、もう一つの障害として、組合員の意識があった。労働組合が組合員アンケートで、適正な残業時間は?と問うと、30~40時間程度(日当たり2時間程度)という答が多かった。1980年代は自動車産業の賃金は相対的にまだ世間の中位水準にあり、組合員も残業をして給料を稼ぎたいという気持が強かったのである。
トヨタ労組の執行部では、まず、将来の夜勤廃止も視野に、日々の残業を抑制することが、会社にとっても、従業員にとっても好ましいことを会社人事部と話し合った。
当時の人事部門は、この点について理解を示してくれた。何故なら、総労働時間1900時間台という目標は共有できていたので、1日8時間で連続2交替勤務とし、残業は日当たり1時間程度しかできなくなっても、昼夜2直から連続2直にすれば、深夜勤務手当と深夜割増賃金の分だけコスト減になるからだ。
また、完全二直の場合には土曜出勤は問題が大きかったが、連続二直であれば、土曜出勤もある程度柔軟にできる。急な生産増に対し、1回の土曜出勤で8時間の残業対応ができるから生産の平準化も図りやすくなる。ただ、深夜勤務手当減少で経営側にはコスト削減のメリットが生じるものの、組合員にとってはかなりの収入減(40歳程度の組合員で月2万円程度)ともなることから、提案する際に大きな議論になることが予想された。
トヨタでは、このように、会社の施策転換に当たる大きな改革をするときは、事前に組合と人事の労務担当者で大きな方向性を話し合うという慣行があった。私の在任時代にも、会社から逆に「労働組合からこんな提案をしてはどうか」という投げかけを受けたことも結構あった。こうした根回しをもとに、労働組合として、残業削減に向けた世論形成に入っていった。
ノー残業デー
労働組合は、残業低減を目指す第一歩として、まず水曜日をノー残業デーにすることを提案した。私たちは、以前から1週間のうち金曜日の直効率(ライン停止なしに動く割合)が高いことに注目していたからである。ノー残業デーを作ればその日の直効率は上がるはずだとの確信があったからだ。やってみると、水曜日の直効率は格段によくなった。残業がなく早く帰れることで作業者は張りきって働くからである。
この施策は組合員の評価も高かった。残業がなければ6時には家に着くから、家族と過ごせる時間も増える。ワークライフバランスという言葉はなかったが、その走りを指向したわけだ。
夜勤廃止の実現
私達はこのようなことを試行錯誤しながら、現場だけ休憩時間を無給化し、所定労働時間を7時間50分とし、昼休みも45分にして、直間の時間確保もできるようにし、満を持して、1993年に連続2交替への移行を提案し、討議を始めた。案の定、深夜勤務が減ることで収入減となるという反対の声が噴出した。
また、夜中の2時近くに帰宅する人もでるから家族の反対もあった。しかし粘り強く職場討議を重ね、理解を広げて、労働組合からの申入れた労使協議も重ね、2直目の残業を限定的にすることなどを約束させ、職場に妥結提案した。評議会での採決の日、執行部には緊張感が走ったが、過去にない二桁の反対票は出たものの、賛成多数で提案は通った。そして、1994年からトヨタの現場で、夜勤のないカレンダーが組まれた。
人間は、夜は寝るというバイオリズムが体内に存在している。たとえ午前2時からでも夜眠るリズムに変わることで、実際、現場の人達の表情も格段に良くなった。2年もすると元の昼夜2交替が良かったなどという意見は消滅した。
トヨタではこのあと2004年ごろには年休のカットゼロ(完全取得、一人平均17日程度)も達成し、本田と並んで労働時間で製造業のトップを走るようになった。夜勤廃止と年休の完全取得、トヨタ労組もやっと本田労組に並んだ。約20年の努力の積み重ねであった。労働組合が総労働時間の制約を強くしたことで、トヨタの企業体質も相当強くなったはずだ。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。