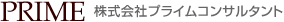たかが100円されど100円(上)(春闘小史・序章)

第18回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
トヨタの「ベアゼロ」回答
利益1兆円を達成したにも関わらず、労働組合の1000円のベア要求に対し会社が「ベアゼロ」で答えたトヨタの2002年春闘は、当時の世間を大いに驚かせた。
歴史の変わり目というのは、その最中に目に見えてそれと分かる場合と、かなり後になって理解できるようになる場合がある。労働組合のナショナルセンターが統一された1989年の「民間連合誕生」という出来事は前者の例だが、このトヨタのベアゼロは後者の例のようで、今振り返ると春闘ばかりか、日本経済の配分構造の変曲点となっていたことが分かる。
では、何がどう変わったか。
それまでの春闘においては、ナショナルセンターが統一要求を掲げ、その時々にいわゆる相場をリードできる組合を先頭に立てて闘う「春闘方式」というものに対して、労働組合にも組合員にも求心力が働いていた。ところが、この赤字でもないばかりか日本一の利益をあげたトヨタでも「ベアゼロ」回答であったという事実により、その求心力がしぼんでしまったのである。
ベアゼロ回答は当時の経団連会長をしていた奥田氏が、「トヨタを頂点にした賃上げ構造を見直せ」というサインを送るために出したのだと私は考えたが、連合も経済界も、そのようには受け止めず、その後も「春闘」をこれまでの延長線上でやり続けた。その結果、組合員の賃上げへの求心力が極度に低下することになってしまったといえる。
その過程を振り返ってみると、労働組合の賃上げは苦難の道を歩んだ。トヨタ労組は2002年から今年までの14回の賃上げ要求で、三度ベア要求を見送り、五度ベアゼロに終わっている。
さらに、ここ2~3年の春闘では、賃上げに政治介入を許してしまっている。春闘は労使自治の下、日本経済成長の果実を労働者側にもまんべんなく配分させる「国民運動」なのだという高度成長期には社会全体が持っていたコンセンサスがなくなってしまったから、政治介入などという情けない現象を許したともいえる。
春闘の歴史を簡単に振り返ってみよう。
高度成長を支えたエンジンとしての春闘
毎年春3月から5月にかけて、一国のほとんどすべての企業労使(公務部門をも含め)が、ナショナルセンターの旗の下、賃上げに取り組むのが「春闘」である。このような社会現象は日本にしか存在しない。
その歴史は、1954年(昭和29年)に遡る。当時合化労連の委員長だった後の総評議長太田薫氏は、合化労連など5単産の共闘を結成して統一闘争を組んだ。力のある産別が前面に出て、ストライキを背景に少しでも高い賃上げ水準を確保し、より多くの労働組合に波及させようという考えだ。
これは、1958年(昭和33年)に太田氏が総評の議長になり、春闘を称して「お手々つないで信号を渡る」と、国全体のレベルでの共闘を呼び掛けたことで、その性格をより鮮明にした。
つまり、その時、ストで戦えて、高い水準を引き出せる産別がまず先行して回答を引き出し、それを他の大手産別が追いかけ、電力や全電通(今のNTT)など全国を掌握する公益部門が追随することで、地方中小に波及させる。最後は人事院が、その結果を踏まえ「民間準拠」の原則に立ち、公務員の賃上げ水準を勧告する。これが「春闘」の戦略的枠組みである。
このように、ナショナルセンターが全国規模で統一要求を組み、回答水準を平準化しようという運動が理念として通用したのは、日本が産業横断的に年功序列賃金であったからだ。
この年功序列賃金というのは、日本の労使関係の三種の神器の一つであると言われた。なぜなら、それは企業への求心力、生活の安定、消費の拡大をもたらし、日本の高度成長を支える原動力となってきたからであった。
年功序列賃金と春闘
年功序列賃金は日本独特の制度である。これが社会制度として定着したのは、戦後の日本が復興を遂げるなかで、猛烈な人手不足を賃金の安い中卒、高卒の新卒社員で補い、これを毎年4月に生計費上昇に合わせて昇給させるという仕組みが産業を超えて出来上がったからである。
生計費という賃金の一側面だけとらえれば、国民のニーズとも合致したから、その平均賃金の引き上げに国家レベルで取り組むことは運動としても分かりやすかった。
しかし、欧米では職務ごとに賃金が決められる職務給制度となっており、賃金は仕事の対価であると考えられているから、賃上げについても同種産業ごとにその成果や生産性に応じた要求がたてられ、それぞれ適切な時期に交渉され、それぞれの水準に落ち着いていく。
国家的統一要求などでは説得力はないし、労働組合もそれは求めない。世界中でナショナルセンターが、賃上げの統一要求を決め、賃上げ闘争の指揮をしているのは日本だけである。それが続いているのは、日本がいまだに年功序列賃金を脱却していないことの証左でもある。

春闘の主役交代
日本独特であるにせよ、大手産別が作り出す世間相場に、産業や規模や官民を超えてある幅で追随するという仕組みは、赤字企業でさえ従わなければならない社会の縛りを生んでいたから、日本経済が右肩上がりに成長していた時期は大いに効果があった。
春闘をより効果的にするために、相場形成役の先頭集団を交代させる戦略性も生きていた。初期には、石炭や化学が先頭で引っ張ったが、次第に鉄鋼や造船などの基幹産業が先頭集団を担うようになるといった具合である。
春闘の主役交代の歴史を見ると、一番大きな変曲点は第一次オイルショック(昭和49年)だった。それまでは、春闘要求は雇用者の家計を調査し、あるべき生計費に追いつくことを目標に決める総評系の運動が主役を演じていた。
当時は、物価上昇が急だったから生活は厳しく、その年の生産性向上を上回るような要求を組み立てることもあった。そういう賃上げは、コスト吸収のための価格上昇を呼び、オイルショックの年には25%という高賃上げを実現したものの、物価上昇も24%となり、狂乱物価と呼ばれる悪循環に入ってしまっていた。
このころ、春闘で次第に相場形成役を担うようになっていた金属産業の産別(金属労協=IMF・JC)の主力を担う8企業(新日鉄、日本鋼管、三菱重工、石川島播磨重工、日立、東芝、トヨタ、日産)の労働組合は、このような賃上げと物価の上昇スパイラル現象に危機感を持ち、前年の生産性向上を超えるような賃上げ要求は控えるべきだとして「経済整合性論」を提唱した。
そして当時の福田大蔵大臣、日経連の桜田会長などとも水面下で協議し、1975年春闘の要求については、前年の物価上昇24%を下回る20%に抑えた。回答は15%であった。
このIMF・JCの取り組みにより物価上昇は次第に収束していき、賃上げ水準も物価上昇分を引いた実質賃金の上昇では、昭和40年代後半を上回るようになった。この選択があったからこそ、世界の中で日本が先行してオイルショック後の経済混乱を脱出できたのである。それは、なによりその後の歴史が証明している。春闘の主役は、1975年を境に完全に金属労協が担うようになったのである。
ただこの当時、職場は30%賃上げを掲げ、戦う姿勢を鮮明にしていた総評の国民春闘共闘会議に比べ、低水準の要求しかしない金属労協の姿勢に対し不満をぶちまけた。しかし、当時のリーダー達は、毎年の要求案決定、回答妥結の度に組合員に経済整合性論の正しさを訴え、この路線を定着させていったのである。トヨタ労組でも、この時代に私は職場委員をしていたが、執行部の弱腰を責める声が強かった。
しかしトヨタ労組は、持ち前の「徹底した話し合い」を職場と交わす一方、ストを前面に産別闘争を強化していた総評系の私鉄総連や化学系の産別を横目に、「ストライキより徹底した話し合いの方が強いのだ」と言い張り、会社にもいずれ日本一の賃金になろうという目標を共有させ、徐々にではあるが賃金レベルを高めていくことになる。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。