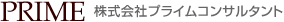プライムコンサルタントのあゆみ
コンサルタントとしての歩みと私たちの基本スタンス
1988年
創業者・菊谷寛之、弥富先生との出会い
プライムコンサルタント創業者の菊谷が賃金コンサルタントになったのは、賃金管理研究所の初代所長・故弥富賢之氏の『合理的賃金の決め方』(ダイヤモンド社)という書物との出会いがきっかけでした。
もともと菊谷は人事労務管理の専門誌『労政時報』(当時・財団法人労務行政研究所、現・株式会社労務行政)の編集部員として毎年の賃上げや初任給、賞与、モデル賃金などの調査をしながら、大企業の人事処遇制度の事例紹介を行っていました。
そんなある日、編集部の資料棚の中に赤茶けた『合理的賃金の決め方』を見つけ、読んでみて、たちまちその完成度の高いロジックの素晴らしさに引き込まれたのです。
弥富先生は、元・人事院で国家公務員の俸給表の仕組みを研究されていた東大卒のキャリア官僚です。その合理的な手法が本田宗一郎氏と藤沢武雄氏の目にとまり、スカウトされて本田技研の賃金制度の基礎を作りました。本田技研が急成長し、その手法が有名になって、賃金コンサルタントになられたという異色の経歴です。
ちょうど弥富先生のほうでも若手のコンサルタントの卵を探されており、菊谷はぜひ話を伺いたいと研究所に押しかけました。そして、その英明なお人柄に接しているうちに、いつしか駆け出しの賃金コンサルタントになっていたのです。

菊谷寛之、都道府県別モデル本給表を開発
当時、中小企業では「弥富式」の賃金体系が広く浸透し、仕事は大忙しでした。菊谷は若さの勢いで全国を走り回り、年に20社以上の賃金制度導入をお手伝いしていた時期もありました。
菊谷が厚生労働省の賃金構造基本統計調査を分析し、『都道府県別モデル本給表』を開発したのもその頃です。これは今も『都道府県版・等級別賃金表』として、当社で出版を続けています。
1995年
菊谷寛之、処女作出版
菊谷の処女作は、『小さな会社の給料とボーナスの決め方』(1995年、中経出版)という本です。当時は、中小企業向けの分かりやすい賃金の解説書がなかったようで、この出版が機縁となって厚生労働省「中小企業賃金制度モデル等作成委員会委員」を委嘱され、賃金表のつくり方や諸手当の決め方などの賃金テキストをまとめたりしました。

菊谷寛之、独自の手法を確立
バブルが崩壊、不況が深刻になって、経営者の間から「定期昇給を積み上げる方式では、中小企業は体力的にやっていけない」「高くなりすぎた賃金を修正したい」という声が上がるようになりました。大いに悩んだ末に、菊谷のたどり着いた結論は次のようなことでした。
(1)少子高齢化とデフレ、雇用の流動化、非正規雇用の増大で、日本の年功賃金は徐々に解体・崩壊する。
(これは、まったく予想通りでした)
(2)これからの賃金・評価制度は人基準の能力主義ではなく、仕事基準の実力主義になる。
(これは半分その通りでしたが、半分は予想外れでした。現状は、人基準と仕事基準とを程よく調和させる混合型の賃金・評価制度が主流になっています)
(3)賃金(基本給)は働く人の生計費をカバーすることはもちろんだが、基本的にはその人に求める役割責任の高さと実際の貢献度の評価によって決定すべきもの。
(この等級の考え方を菊谷は「責任等級」と名付けました)
(4)同じ役割責任で評価が同じでも、賃金の高さによって昇給幅は違う。賃金の低い人は大きく昇給しても、賃金が高くなるに従い昇給は徐々に抑制するのが自然である。
(調整年齢による昇給の抑制ではなく、賃金表にゾーンを設け、賃金の高さによって昇給を抑制する「ゾーン型賃金表」と「段階接近法®」という方式を考案しました)
(5)評価に見合う賃金の高さになったら、(ベースアップ分は別として)昇給は停止して構わないし、賃金の高さに見合う貢献度が認められない場合は、マイナス昇給もあり得る。そうしないと、厳しいデフレで限られる総額人件費を若手や優秀人材に配分できない。
(2000年以降、2013年まで、毎年の春闘は「ベア・ゼロ」が続きました)
(6)一般的な勤務成績の判定や相対評価のロジックによる賃金査定だけでは説明力が乏しく、社員のヤル気につながらない。これからは、事業の戦略やビジョンと評価を連動させ、目標や仕事を基準とする業績評価と行動評価を取り入れるべきである。
(この方式を「成果目標管理プログラム」という資料にまとめました)
(7)目標設定やフィードバックの時は評価者が部下と面談し、社員の目標達成意欲や経営参画意識を高め、育成につなげることで組織が活性化する。
菊谷はこの考え方を広く世に問うてみたいと考えたものの、当然のことですが、当時はなお弥富式を信奉するクライアントも非常に多く、研究所の中での活動にはどうしても限界がありました。
1999年
菊谷寛之、独立と同時に株式会社プライムコンサルタントを設立
そこで思い切って、菊谷は弥富先生のお許しをいただいて独立することにしました。
「温かく理解していただいた先生や応援してくれた同僚のコンサルタントの皆さんには、いまでも深く感謝しています」。菊谷は今でもそう述べています。 独立したときから、菊谷は法人形態のコンサルタント事務所を目指そうと考えていました。個人ではどうしても限界があると感じていたからです。
「クライアントの皆さんは、事業を長期的に存続・発展させるために、計画的な人材の育成や活用を期待して人事制度や賃金体系を整備しようとされます。それをお世話するコンサルタントが個人開業では、大きな不安を持たれるのでは」と菊谷は感じていました。
そうして誕生したのが、株式会社プライムコンサルタントです。資本金1,000万円で法人登記するとともに、東京都千代田区二番町に事務所を開設し、営業を開始しました。
2000年
菊谷寛之著「給料を責任等級制で正しく決める本」出版
菊谷は、開発した賃金ロジックと業績評価の手法を『給料を「責任等級制」で正しく決める本』(2000年、中経出版)という本にまとめ、セミナーや執筆活動を開始しました。
幸い数多くの中堅・中小企業の賛同を得て、またもや仕事は大忙しとなりました。

2002年
組織体制の充実・拡大
人事・賃金制度の導入や運用をサポートするには、経営全般の基本的な知識はもちろん、具体的な相談に始まって、診断から分析、解決策の企画立案、実行支援、アフターサポートまで、継続的な取り組みが必要になります。
また、コンサルタント事務所も一つの商売ですから、新たな商品開発や、マーケティング、販売促進、顧客管理などの業務も並行してこなしていかねばなりません。 ささやかなものとはいえ、組織的な取り組みが必要でした。幸いに知遇をたどって、菊谷の考えに賛同する元気で頼もしい社員たちが参加することになりました。
経営成果に結びつく業績評価の手法を確立
仲間のコンサルタントも増えたので、仕事の範囲をさらに拡げようと、まず取り組んだことは、経営方針から組織目標、個人目標へとブレイクダウンし、各人の自律的な活動を促す業績評価の仕組みづくりでした。
キャプラン/ノートンの「バランス・スコアカード」の手法を取り入れたり、主体的な業務プロセスの改善を動機づけるための「達成行動ガイドリスト」を開発したりして、評価制度の改善に力を入れました。そのあたりの考え方は、「新実力型賃金のつくり方」(2002年、日本経団連出版)に詳しくまとめてあります。
2005年
菊谷寛之著「中堅・中小企業の業績連動賞与」出版
「いざなみ景気」によって企業の利益水準は回復しても、毎年の賃上げは「ベア・ゼロ、定期昇給分のみ」というデフレのパターンがすっかり定着し、限られた人件費を少しでも有効に活用しようと、賃金体系や賞与の見直しを進める企業が増えていました。
各方面からのセミナーの依頼やクライアントの皆さんの相談に対応するため、皆で手分けして全国を飛び回りました。 企業業績に連動した弾力的な賞与原資の決定と、貢献度に基づく賞与の個人配分のやり方を解説した「中堅・中小企業の業績連動賞与」(2005年、日本経団連出版)を出版したのもその頃です。
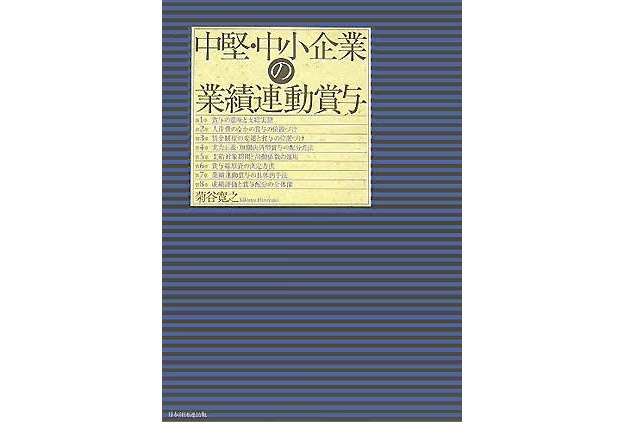
2008年
リーマン・ショック
ところが、忙しい仕事の割になんとなく満足感が得られません。
大事に設計した賃金・評価制度をせっかく導入してもらっても、うまく使いこなせない、あるいは少々持てあまし気味のクライアントが多いようなのです。
仲間のコンサルタントも同じような思いを抱いていました。
「ひょっとしたら、何か大事なことが抜け落ちているのではないか」、そう感じ始めた矢先、2008年のリーマン・ショックが発生したのです。
クライアントの業績は急降下し、当然、私たちもあおりを受け、危機感を抱きました。
目の前では、多くのクライアントが経営不振から抜け出せず、苦しんでいます。
私たちのコンサルティングは、果たしてクライアントの利益になっているのだろうか…真剣に悩みました。
マネジメントの基本をつかむ
いろいろ模索するうちに、私たちはドラッカーのマネジメント理論やゴールドラットの制約条件理論(後述)の勉強にのめり込んでいきました。
ドラッカーを体系的に勉強して分かってきたことは、企業そのものの目的・ミッションの重要性です。 企業はイノベーションによって顧客を創造し、顧客に価値を提供するために組織全体で成果を上げねばならない、と明快に説かれていました。
最も成果が上がる事業領域に経営資源を集中するために、経営者は最適な組織構造を作って有能な人材を登用し、目標を明示し、働く人たちの自主性を尊重して仕事を任せていきます。
それに呼応して、部下に強みを発揮させ、その働きを評価して正当に報い、人材を開発し、部下とともに成果を上げることがマネジャーの仕事なのです。
驚いたことにドラッカーは大変な日本びいきで、高度成長期に急成長を遂げた日本企業を大いに参考にして、マネジメントの体系を作り上げていました。 日本の若手経営者(当時)もドラッカーを猛勉強して事業を伸ばしました。両者は師弟の関係を超えて、まさにウィン・ウィンの関係にあったのです。
小さな会社の経営者であることを自分も意識するようになって、ようやく基本的な経営管理と人材活用のつながりが飲み込めてきました。
苦悩の時期
ドラッカーは「企業の目的として有効な定義は一つしかない。すなわち、顧客の創造である」と喝破しました。「現代の経営」(1954年)という本の有名な一節です。
一方、「ザ・ゴール」(1984年)の著者ゴールドラットは、企業の目的は「現在そして将来にわたって利益を増やし続けること」であると断言しています。
別々のことのように聞こえますが、それぞれ企業がめざすゴールの本質をシンプルかつ見事にとらえていると思います。
少し具体的にいうと、企業は市場の新たな需要を生み出す魅力的な商品やサービスを開発して、自らの顧客を増やし、息の長い商品をできるだけ多く販売して、利益を上げ続けるのです。
それによって従業員の雇用を守り、人材を育成して、新たな事業投資を行い、社会を支える公器として存続することが可能になるのです。
そのためには、経営者と従業員が力を合わせて常に市場と対話し、現場から学習し、仕事を創意工夫し、新たな課題に挑戦し、問題を解決し続けなければなりません。
賃金・評価制度を導入したり改善したりするのは、そのために一人ひとりの力、そして組織の集合的な力を引き出し、自信をつけさせ、人件費を有効に活用して働きに報いるためだったのです。
しかしバブル崩壊後、大半の日本企業はコストカットで利益を確保するデフレ的な対症療法に走る傾向が強まっていました。
特にリーマン・ショック後は、賃金・賞与を切り下げたり、雇用を縮小したりして人件費に大ナタを振るう会社が続出し、クライアントはもちろん、私たちも非常に苦しい仕事が多くなりました。
コストカットだけでは、企業はいずれ勢いを失い、限界に突き当たります。
経営が苦しいときこそ、事業にイノベーションを起こすための人的投資を継続し、未来の成長力を蓄える必要があるはずです。
人事領域での専門的な支援を通して、「顧客を創造し、利益を上げ続ける」という企業の目的を未来志向で支えることが、私たちの本来の職業的使命ではないのかという思いが日に日に募ってきました。
そして、私たちがお手伝いしている賃金・評価制度のコンセプトは、本当にこのような企業の目的にふさわしいものになっているのか…自分で発した問いに戸惑いながら、私たちは苦しい自己点検の作業の必要性を感じていました。
2009年
「組織学習」の理念を実践する
これまでの、個人のヤル気を高めるだけの人事アプローチでは限界があると思い知らされ、悶々としていたとき、コンサルタントの一人がピーター・センゲの『学習する組織』(英治出版)という本を見つけてきました。
読んでみると、非常に興味深いことが書いてありました。 世界のつながりがどんどん深まり、複雑性と変化のスピードを増す現代社会では、少数の卓越したリーダーが、専門的な分業体制のもとで分断された個人を引っ張るピラミッド型の組織では立ち行かなくなっているというのです。
組織の競争優位性は、個人と集団の両方の継続的学習から生まれ、組織の中であらゆる役割・レベルを担う一人ひとりが、主体的な対話・学習・思考を重ね、全体性を保ちながら相互に共感・連携して行動できる集団でないと、内部的な成長力を保つことはできない―このようなことが、理論と実践の両面から分かりやすく説かれていました。
組織学習の理念に啓発された私たちは、仕事の合間をぬって社内対話を開始しました。 具体的には、一日に何時間もかけて、次のようなテーマでの自問自答を延々と繰り返したのです。
- 自分たちは何のためにコンサルタントの仕事をしているのか
- クライアントは私たちに何を期待しているのか
- クライアントの経営システムとはどんなものか
- 組織に貢献しようという個人の内発的な動機はどのようにして生まれるか
- そのとき、人事・賃金・評価はどのような役割を果たすのか
- これからのコンサルティング・サービスはどのようなものが求められるのか
結論を出す会議でもなく、議論で勝負するディベートでもなく、参加者全員でお互いに経験を内省し、本音を語り合い、傾聴しながら物事の全体を探求する対話(ダイアログ)を実践し続けました。
次第に私たちのセミナーや営業方法、コンサルティング、アフターサービス、すべての仕事のやり方がクライアント重視の未来探求型のものに変わりはじめました。
それまではどちらかというと、自分たちが考えた賃金・評価制度のパッケージ・モデルをクライアントに売り込み、カスタマイズを終えて納品し説明するという「システム」を買ってもらうサービスに近いやり方をしていました。
しかし、他人が作り込んだシステムを使いこなすことは、誰にとっても容易ではありません。
私たちが苦労して制度を作り込んでも、クライアントの皆さんが浮かない顔をしていた原因は、まさにこれだったのです。
現在
対話手法のコンサルティングスタイルを確立
いまはむしろ、顧客がやりたいこと、できることを中心に置いて、私たちにできることは何かを見極めることに力を入れています。
われわれの知識やノウハウを知ってもらい、クライアントが自分たちで使える賃金・評価制度を一緒に作り込み、早めに使ってもらう、「相手の効用」を重視したコーチングに近いやり方に変えて、お互いに仕事が楽しくなってきました。
社内対話で鍛えたお陰で、依頼先の中でのコミュニケーションもうまくとれるようになりました。クライアントの間で意見がまとまらないことがあっても、できるだけ本音の対話を促し、実情に寄り添った仕事ができるようになりました。
最近では、この対話の手法をクライアントの組織開発にも活用し、社員全員が参加して組織の将来ビジョンを共有する大規模な対話集会を開いたりしています。
いま振り返ると、自分たちのコンサルティングのスタイルを確立するうえでも、サービスを改善するうえでも、「顧客の声に耳を傾け、顧客に起きていることの全体に目を向ける」ことにいつも気を使っていました。
そして自分たちの限界に気づき、新たな発想で仕事に取り組んだとき、理論や手法の面でも転機を掴むことができたように思います。