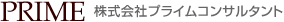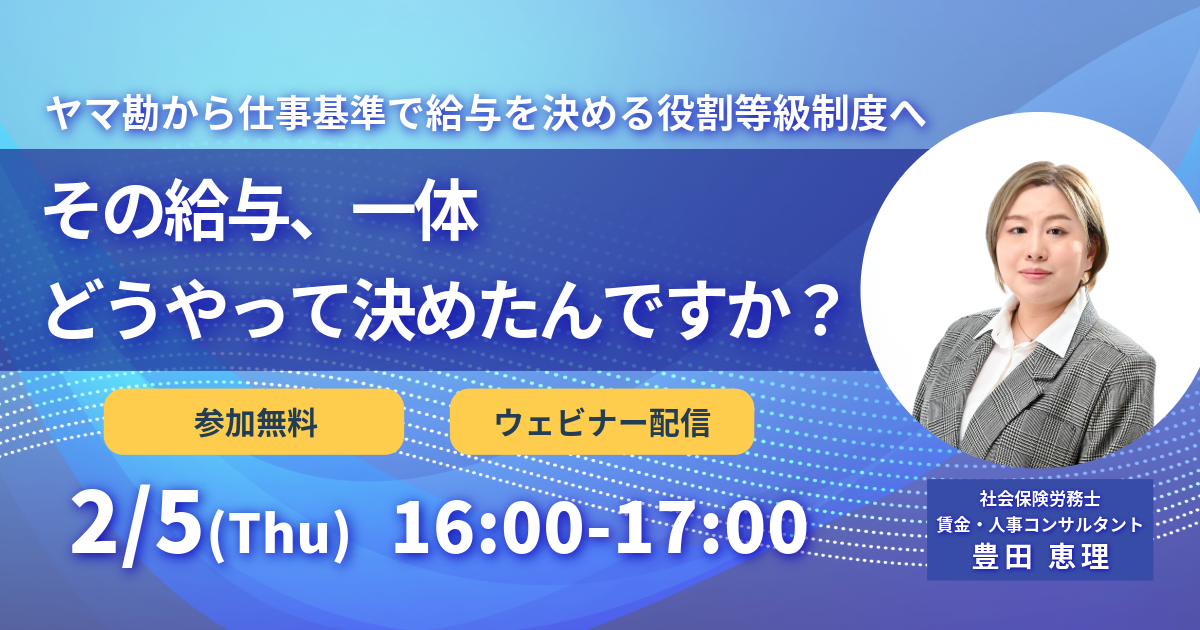夜勤廃止への道のり(中)

第22回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
モータリゼーションの幕開け
トヨタは昭和30年代に自動車生産が毎年5割増しで伸びていた。昭和36年には日本における「国民車構想」の第1弾としてパブリカを発売し、その投資を現有人員で生かしきるためには、工場の稼働時間を飛躍的に延ばす必要があった。
パブリカは、サラリーマンでも車を持てるようにと、1000ドルカー(当時1ドルは360円だったから、約36万円。月給が約3万円だったサラリーマンが年収分で買える価格だった)として発売された。
そう宣言した以上、この車を日本のモータリゼーションの先駆けにしなければならなかった。その狙いは間違いではなく、それまで昭和30年代に生産台数5割増しの原動力となっていたトラックに代わり、昭和37年以降は、乗用車が5割増しで伸びはじめ、昭和41年には乗用車の年間生産台数がトラックを上回った。
昭和41年はカローラを発売した年であり、まさに日本のモータリゼーションが幕を開けた年でもあった。その生産増を可能にしたのが、昼夜二交替勤務であったことは間違いない。
しかし、昭和20年代、30年代に入社した若い世代が次第に中堅となり、家庭を持ち、40代に差し掛かってくると、週6日稼働の昼夜二交替勤務はつらくなってきた。労働組合としては、中堅世代の組合員が、1週間働いた疲れを癒し、かつ家族とも過ごせる時間を確保できるよう、何としても週休2日を達成する必要があった。
週休2日制の実現
製造現場を週休2日にしよう、という方針は、組合執行部発のトップダウンの方針という色合いが濃かった。それは、一つには、働くことを美徳とする多くの現場労働者の意識の底には、「休みを増やす」ことに対する罪悪感のようなものがあったからである。
そして、会社はといえば、経営者は口を開けば「時間は命だ」というのであるから、会社思いの組合員は「週休2日にしてくれ」とは言い出しにくかったと思われる。
しかし、執行部にしてみれば、当時世の中は週休2日の流れができつつあると感じていたうえに、トヨタにおいては、戦後に採用された中核社員が30歳代となり、子どももいる家族を形成するようになってきていたから、早く週休2日にして組合員が家族と過ごせる時間を確保してやらなければという思いが募ったのだと、この取り組みを主導した梅村氏は言っていた。
昭和40年代半ばには、松下電器などで週休2日が実現した。執行部としては、焦りも感じたはずだ。そうした中で、週休2日の必要性を水面下で会社にも訴え、まずは一歩を踏み出すことだと、昭和47年に、週休2日の必要性を職場と共有する狙いで、土曜日の夜勤を止めることを考えた。
しかし、それだと現場だけ労働時間が週当たり4時間短くなるため、オール昼勤職場では土曜日を半日就労、つまり土曜半ドン制としてはどうかと、会社からも建設的な提案を受け、変則ではあるが週休2日が実現した。
この働き方が実現してみると、やはり、土曜の夜勤がないことで体が楽だという声が強くなり、週に2日休んでもすることがないなどという声も少なくなってきた。
そこで、執行部は当時、週6日稼働、日当たり7時間労働であったものを、日当たり8時間労働の5日稼働、週40時間労働にすることを提案した。半ドンの試行が成功し、週休2日に反対する声は弱くなっていたが、それでも日当たり拘束時間が1時間長くなることで、就業後の「習い事」に間に合わないなどの声も出たようだ。
しかし、製造現場に5日働き2日休むリズムが必要という執行部の信念に基づくリーダーシップで職場との議論を乗り切り、とうとう昭和49年には週休2日制のカレンダーが実現した。昼夜二交代制を導入してから、12年が経過していた。
時間は命と言っていた会社であったが、組合員の命と健康を守るという主張に、土曜半ドンなどという知恵も貸してくれながら、理解を示してくれたのであった。
休日増をめざす自動車総連共闘の構築
自動車産業は、人でなければ組み立てられない労働集約産業という特徴がある反面、設備が重厚である装置産業の性格も併せ持っている。そうした特徴を効率的に生かすには、週途中に休みが入ることは好ましくないことになる。
週途中の休みは働く人のリズムをも壊す。そこで、週途中に国民の祝日が入る場合は、その日は出勤して、一年分のカレンダーの中で、お盆時と年末年始に5日ずつ振り替えて集約し、夏休みと冬休みを作るようにした。
こうしたカレンダーで、夏休み、冬休みを最低1週間確保し、かつゴールデンウイークも1週間の休みを確保するとなると、年間休日がどうしても120日必要になる。年間休日120日を確保したうえで、週8時間労働となると年間所定労働時間は1960時間だ。
週休2日制を実現した昭和50年の所定労働時間は2000時間だった。そこから40時間、5日の休日増を図ることは、自動車産業の競争力にかかわる重大な問題であった。
そこで、自動車総連はこの問題を、企業ごとのカレンダー問題としてではなく、産業全体の問題としてとらえ、自動車総連でメーカー組合の時間共闘として取り組むこととした。産業内で各社が稼働する時間を共通にしなければ、競争条件がそろわないという発想が出てきたからである。
昭和47年に結成した自動車総連は、2年後の昭和49年に世界を襲った第1次オイルショックをきっかけに、低燃費の小型車を得意とする日本車が、世界中で売れ始めたことによる貿易摩擦問題や、生産規模の増加を背景とした国内での過当競争、自動車をぜいたく品としてかけられてきた高い税金の減税要求といった産業政策への取り組みを強化していた。
そんな空気であったから、自動車総連に集った意味合いとして、休日増を共闘で取り組むという方針への求心力は大いに高まった。しかし、稼働日を1日削るということは、労働時間を一気に8時間減らす事を意味するから、経営上大きなコスト増になる。経営者の抵抗は非常に強く、取り組みは簡単には進まなかった。
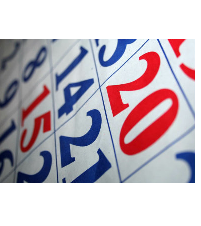
内外の圧力と共闘の成果
自動車総連は、この休日増の取り組みに外圧を利用した。当時、全米自動車労組(UAW)は、日本は長時間労働で作り出した自動車でアメリカに対して失業を輸出している、と日本の自動車産業を批判していた。
これを受け、自動車総連は、当時年間休日が120日程度あったアメリカと休日水準を合わせ、批判に応えるべきだと強く主張したのである。
もう一つ休日増の取り組みを後押ししたのは日本国内の追い風であった。それは、1985年に発表された「前川レポート」だった。
前川レポートでは日本の長時間労働体質からの脱却がうたわれていた。これを受けて、通産省や労働省が、「時短推進」を掲げ、年間1800時間労働の旗を振り始めたのだ。
こうした内外圧力を最大限活用するため、自動車総連は、それまで休日増の取り組みについては、メーカー毎に、秋に、自社のカレンダー協定の取り組みとして取り組んでいたのを、1990年に、賃金引上げとの同時取り組みとして春に一斉に取り組むこととした。それも、それまでの1984時間から一気に1960時間へと休日3日増を要求したのだった。
実は当時、本田は既に1976時間と休日数で一歩先んじていたから、共闘することによってトヨタも日産も少なくとも休日1日増は獲得できる胸算用はあった。
そして春の共闘をしたのだから、本田がさらに1日進めば、トヨタも日産もさらに1日進む。1968時間にしておけば、あと1日は来年でもいいと考えていた。
ところがふたを開けてみると、時短ではホンダの後塵を拝していた日産が一気に満額である休日3日増を確実にしたという情報が最終版に聞こえてきた。
その時トヨタは、2日増で労使が概ねまとまっていたのだが、日産が3日増であるなら、トヨタも何としても同水準を引き出さなければならないと、当時の委員長を先頭に社長に直談判をした。社長は、回答日の1日前に満額回答を決断してくれた。共闘の効果が最大限発揮された取り組みだった。
しかし考えてみると、経営者にとってみても、当時、稼働日という競争条件をそろえることは過当競争抑止のため、必要なことであったろうし、休日120日の水準を達成することは、そのころ年間休日がやはり120日程度であったアメリカと肩を並べることになるのだから、「失業を輸出している」というアメリカからの批判を和らげる意味もあったはずである。
この時点で、日本の自動車産業は、車の品質や生産性だけでなく、労働者の働き方においても、ほぼアメリカに追いついたと言える。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。