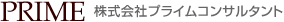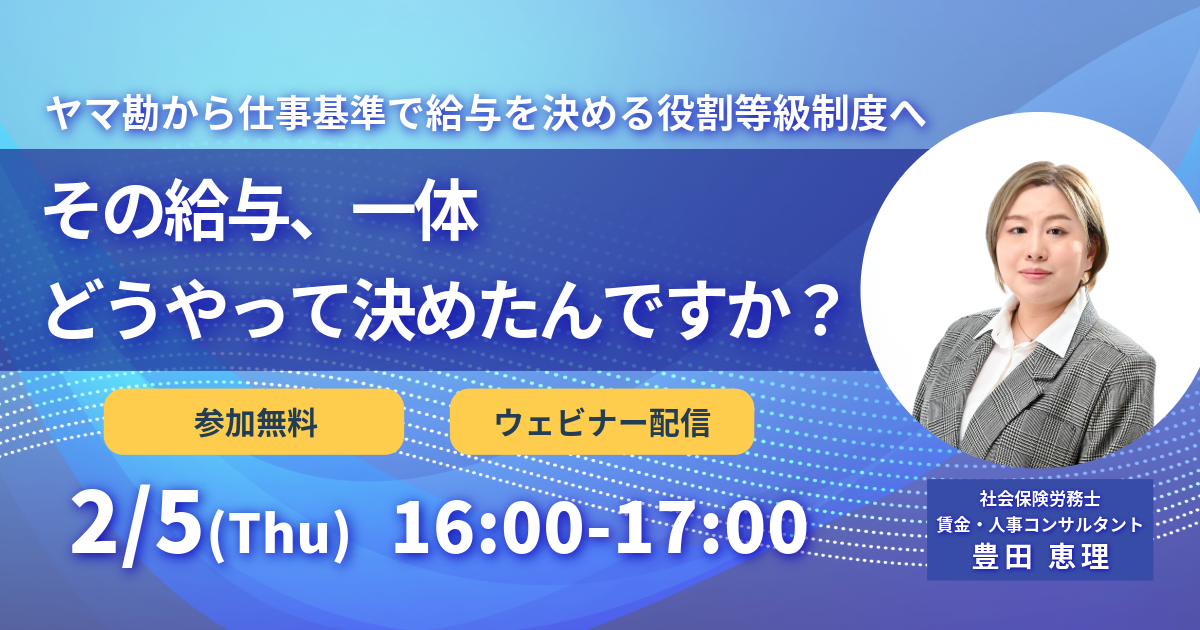賃金の『見える化』(上)

第16回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
売り上げ目標のない会社
前項で、トヨタの現場が「能率」と「原価低減」だけを目安に管理され、現場もそれを目標として働き、それがわずかながら賃金にも反映されることを述べた。
そうであれば、「では、営業部門や管理部門はどのような目標を与えられているのだろう」というふうに興味が移る。実際、現役のころはよく質問された。そして、その答えはたいていの質問者をびっくりさせることになる。
トヨタは、生産現場に台数や利益といった、外部環境に左右される数値目標を掲げないだけでなく、営業部門や管理部門に対しても、部門や車種単位に売り上げや利益目標を課すことはない。そもそも会社自体が、決算発表の場で来期の売り上げを何兆円とか利益何兆円、あるいは何%増などという目標を語らない。せいぜい「今期並みは確保したい」程度しか明らかにしない。
それは、トヨタが何台作るか、何台売るか、いくらで売り、いくら利益を出すかというようなことは「お客様」である市場が決めることであり、それは景気や為替でいくらでも動くと考えているからである。
トヨタは必要なものを必要なだけ作る、というJIT(ジャストインタイム)の考え方をこんなところでも貫いている。
だから、部門や車種ごとに台数や利益を目標とすることもしない。あるのは、全部門あげて少しでも安く(原価低減)良いものを作ろうという目標だけである。
このように説明すると、クラウンやカローラといった車種ごとに、何か目標がなければ生産計画も立てられないのではないか、と聞かれる。確かにある程度ざっくりした見込み台数は設定される。
しかしそれは、市場の引きによって絶えず変わる。また、カローラ店部が何台販売したからと言ってその数字だけで直接評価されることはない。
逆に、台数がそれほど売れない車種を担当していても、社内で冷たい目で見られることもない。なぜなら、原価を下げるという点で言えば、たとえばコンパクトカーのセグメントでは、多くの部品が共通化されているから、一台でも余計に作れば、それは最量販車であるカローラに使われる部品単価を低減することになるという意味で、原価低減に貢献できるからだ。
トヨタでは、原価をそのようなどんぶりで考えているから、車種単位で目標を決め、評価するということはされない。
この点も、自動車メーカーとしては異質な経営手法であるかもしれない。しかし、トヨタで仕事をしてみると、売り上げや利益の数字に対してはそういうアバウトな考えでしか全社が貫かれていないことを、みなが前提にしていることが分かる。トヨタ労組もこの考え方を支持してきた。
能率とリンクする賃金
売り上げや利益に対する考え方がそんな具合だから、トヨタの賃金制度も戦後から昭和末期まで、基本給の単純な積み上げ方式であった。
定期昇給もあるにはあるが、制度と言えるようなものではなく、毎年、定期昇給込みの賃上げ要求をして、決着した額をこれまでの賃金カーブをにらみながら、個別に配分するというようなやり方であった。
ここで、現場を管理している「能率」と賃金の関係を少し説明しておかなければならない。
従来のトヨタの賃金は、個々人で見ると、基本給およびそれとほぼ同程度の重みの生産手当というものから構成されており、この生産手当が、現場ごとにあげた能率の向上度合いとそのままリンクしていた。
と言うと、給料の半分が生産性とリンクしていたら、生産台数が急激に落ちて生産性が下がったとき給料に与える影響が大きすぎないか、が心配になる。
また、「能率」は現場の「課」単位で算定されているから、かかわる車種や部品により、不公平が出るのではないか、というような懸念も出る。
実際、一部の学者からはそのようなトヨタの賃金制度を称して、賃金の半分が生産性で支配されている不安定な賃金制度であり、働く人の賃金まで能率でしばる非人間的な制度だ、というような批判を浴びたこともある。
しかし、そのような心配はないことは、能率をめぐる労使の話し合いで十分確認されている。
生産手当は、戦後、初めて設定された時から、ひたすら上がり続けている。なぜなら、能率を手当に置き換えるための係数に独特のマジックがあって、少々生産が落ちても下がらないような複雑な方程式で計算されるからである。
それともう一つには、たとえば昭和60年ごろの平均賃金は20万円程度であったが、生産手当の変動は、せいぜい数百円に収まるように係数が設定されていた。
とは言え、実際には現場では、課単位の数字が見えるから、たとえ百円でも競争心は掻き立てられる。がんばれば上に行く数字は現場の作業者を駆り立てた。
このように、日々の生産性の動きと賃金がリンクし、毎月変動する会社を私はトヨタ以外には知らない。この仕組みは、モチベーションという意味では高度成長期に大きな力を発揮した。
一方、管理部門には全社平均の生産手当が適用されていた。現場に比べその変化はわずかではあったが、数字が動くことで全社の生産性がどのように変動しているか大雑把には知ることができた。能率を賃金におきかえた生産手当の仕組みが全社の一体感を支えていたといえる。
限界が見えた賃金制度
賃金制度がこのようなものであったから、評価制度も実に緩やかなものであった。公務員ほどではないが、ある幅で全員が右肩上がりに上がっていく典型的な年功型の制度運用であった。
しかし、それはトヨタが戦後ずっと右肩上がりで成長してきたから可能だっただけであり、平成に入り日本経済が安定成長期に入ると、現場で言えば、誰でもが組長(二十数名を部下に持つ)になれなくなり、管理部門で言えば、誰でもが課長になれるわけではなくなり、制度の限界も見えてきた。
また、組合員からも人事評価が不透明だとか、評価がわかりにくい、なぜあいつが昇格して、俺はできないのか、上司から説明が聞けない。などといった声があがるようになってきた。
このころになると、どこの会社でもポスト不足が言われるようになるとともに、高齢者層の高い賃金が固定費として重くのしかかるようになっており、ポストと資格の分離、能力に応じた昇給の差をつけるため、職能資格制度を導入する企業が増えていた。
トヨタではまだそれほどではなかったが、これまでのような、誰もが上がるから安心といった、古風な賃金制度にいつまでも甘んじていてはいけないという危機意識を労働組合も持つようになっていた。
「進むべきか、とどまるべきか」賃金制度改革の悩み
賃金制度にメスを入れる必要がある、という機運は、こうして組合の中に少しずつ高まってきた。しかし実際に変えるとなると、大きな壁があった。
それは、トヨタの賃金制度が社内では聖域のように見られていた「能率」とリンクするものであったため、労働組合がそこに口を出すべきではないというような空気があったからである。
さらにもう一つの壁として、伝統的な労働運動のイデオロギーの壁もあった。
今では能力や成果で賃金に差が出ることは労働組合でも当たり前と思っているが、当時の左翼的労働組合における伝統的考え方として、人間の価値はみな同じだから年功以外で賃金格差をつけることは許されない、という価値観があった。
だから、典型的な右肩上がりが保証された格差の小さい単線型の積み上げ方式を敢えて能力で差をつけられる賃金制度に変更する提案など、労働組合としてなすべからざることだ、というような意見がトヨタ労組の中にもあったのである。
とは言え、私たち自身にも、一部の学者ほどではないが、生産性の動きにリンクした賃金は、劇的な生産変動があったら賃金が下がるリスクを否定できないという思いがあったし、さらには、10年後に自分の賃金がどれくらいになるかも見通せないような積み上げ方式をこのまま続けていていいのか、という思いもあり、まさに、賃金制度を改革すべきか否か、組合執行部として、悩みに悩んでいたのであった。
しかし、その悩みをうち破ったのは、トヨタならではの「車の両輪」の考え方であった。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。