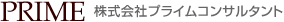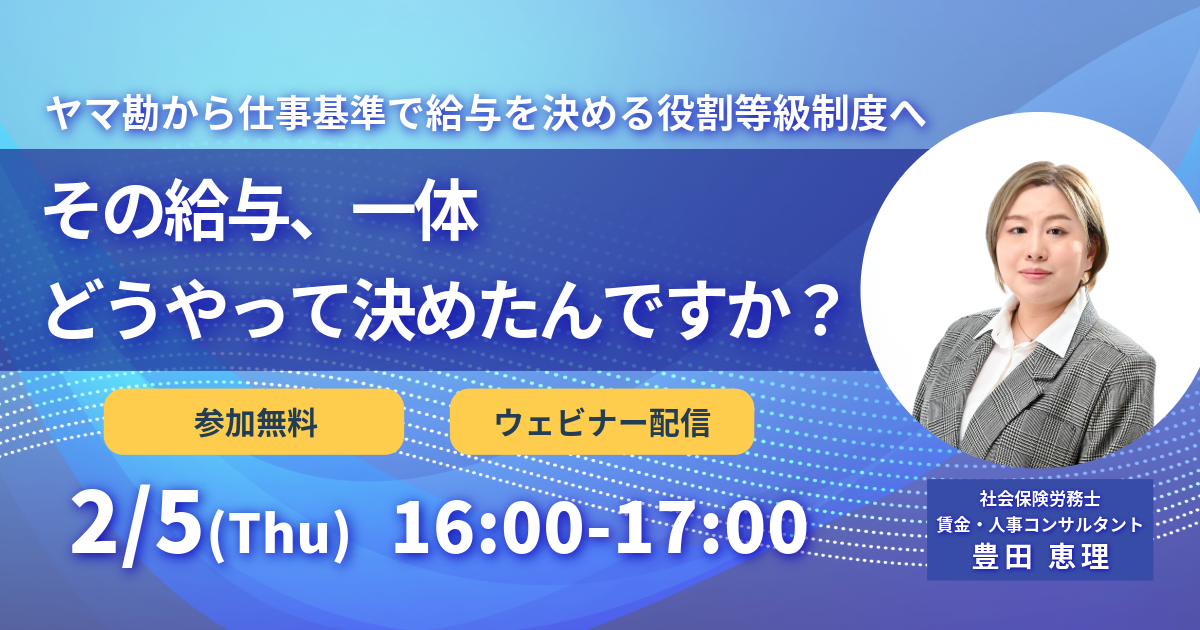労働協約の締結

第14回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
無協約状態との訣別
トヨタのような大企業で、「労働協約が締結された」というと、組合結成のころの話かと思われるかもしれない。
ところが、トヨタ労使がいわゆる包括労働協約を締結したのは、昭和49年だ。どうしてトヨタほどの労使が労使関係を形成するイロハのイともいえる労働協約を作らなかったのか。
そこにはいかにもトヨタらしい理由があるし、またようやくこの時期になって締結したということについても、トヨタらしいといえばトヨタらしい背景があったのだ。
まず、なぜ包括労働協約を作らなかったのか、である。それは、労使とも、昭和25年争議の際の協約(覚書)問題(結んだはずの労使協約が形式の不備で「無効」とされた実体験)が体の奥深くに棘のように刺さっていたことがあるようだ。
もちろん労使は、賃金、労働時間、福利厚生についての労働条件で個別に合意をしたことを労使協定としてその都度締結している。
しかし、組合員の範囲、労使交渉のありかた、争議行為のルールなど労使関係上の約束事を規定した包括協約については、その締結話が持ち上がるたびにつぶれていた。
労働組合内部でも、会社でも、労使宣言を交わした精神が引き継がれているのだから、現状のままでよいのではないか、というような意見が出され、現実にも労使関係上、大きな問題も起きなかったことからそのままにされてきたようだ。
しかし、昭和40年代の半ばになると、IMF(国際金属労連)への加盟や、産別組織を統合して自動車総連を作ろう、というような議論も本格化し、欧米では当たり前にある包括労働協約をトヨタも持つべきだという意見が強くなってきた。
この議論の中心にいたのは、昭和44年から2年間副委員長を務め、その後トヨタでは異例ともいえる11年間に亘り委員長を務めることになる梅村志郎氏であった。
梅村氏は、労働組合が会社と真に対等な関係を築くには、憲法ともいえる労働協約が必要だと、組合内部にも説き、会社に対しても粘り強く説いて回られた。
そして、梅村氏が副委員長になった時から数えれば5年が経過した昭和49年になってやっと労働協約締結にこぎつけることになる。ここにようやくにして無協約時代に幕が降ろされたのである。
労使協議制
組合結成からおよそ四半世紀後にようやく締結された労働協約にはどのような思いが込められ、またどのような特徴があるのか。その第一は「労使協議会」の規定である。
トヨタでは、労使交渉を行う場の名称を「団体交渉」(団交)と呼ばず、労使協議会と呼ぶようにした。労働組合が、組合員の団結力を背景に会社に要求をのませようとする場は、団体の力でやる交渉という意味で一般に「団交」と呼ばれ、ほとんどの組合ではそのように呼んでいる。なぜトヨタでは労使協議会なのか。それには二つの理由がある。
まず、第一は、労使宣言の精神にある「相互信頼」である。それは 第7回で書いた「徹底した話し合い」の精神に行きつく。
ストライキよりも強い「徹底した話し合い」を実践するには、労も使も、その協議の場に臨む者同士、後ろに控える職場役員、管理職層との共通認識の構築が必要になる。
執行部、役員のみが交渉の場で互いに納得しても、それを受け止める者たちが理解しなかったら、相互信頼などありえないし、それだったらストライキにまで進んでしまうだろう。しかし、互いに後ろに控えるものとの一体感、信頼が形成されるまで組織内でも「徹底した話し合い」をしていれば、協議の場でも自信を持って相手の主張を受け止めることができる。
トヨタでは、団交のニュアンスには「力で押し込む」という意味あいがあると考えてきた。その力とは「ストライキ」を打って歯止めとする姿勢のことである。
いずれ後に書くが、トヨタではストによる歯止め基準の設定は、真の意味で組合員の思いを代弁することにならないと考えてきた。
そこで、労使交渉はスト権を背景にした団交で行うのではなく、労使協議で行うということを協約で明記し、互いにその精神を共有することにしたのである。
この徹底した話し合いを労使がいかに大事にしているかを示す「形の上」での実践事項として、労使協議会には必ず社長が出席するという不文律がある。
労働協約には、「労使同数の委員で構成する」としか書いてないが、この不文律は破られることなく今日まで綿々と守られている。
もう一つの理由は、「いわゆる『労使協議制』」を労使交渉の場で実践することを約束することであった。
日本において、昭和40年代においては「労使協議制」には特別な意味があった。最近の労使関係においては、労働組合の経営に対する提言は、それが建設的なものであれば歓迎されるし、労働組合の役割として当然とされている。しかし、日本では、労働組合の経営参加ともいえる経営問題への提言は、一時タブー視されていた。
それは、終戦直後、政党運動に引っ張られた労働組合が、しきりに「生産管理闘争」を標榜し、企業を存亡の危機に陥れた苦い経験があったからである。生産管理闘争とは、労働組合が企業の経営者に代わり、経営の指揮をとるという運動手法である。
当時の社会主義政党が目指したのは「資本家」による国家支配を排し、労働者が支配する国家の実現だった。その、プロセスの一つとして、労働者が経営を支配できるのであれば、企業経営を乗っ取って、「生産管理」をすべきだ。という考え方である。

今、冷静に考えれば、経営に関する広範な知識、取引ルールや、金融機関、取引先の信用等々、何一つない労働組合が経営のかじを取ってもうまく行くはずはないと、誰もが思う。しかし、当時は熱に浮かされたように「生産管理」を掲げる運動がそれなりの支持を得ていた。
しかし、実際、当時労働組合の「生産管理」に行きついた企業が成功した例は皆無である。経営者には、そのような「生産管理闘争」=「労組の経営参加」に対するアレルギーがあった。
一方、労組にもそのように政党に振り回されたことへの反省や、生産管理までは行かないまでも、戦後「生産復興」を掲げ、経営に対し様々な施策を要請したものの、経営危機を救うことはできなかった苦い思い出があり、経営のことは経営に任せようと、「口出し」を自制し続けた歴史がある。
そういう負の意識が、西欧では当然視されていた「労使協議制」の導入について、日本の労働組合を臆病にさせていた。しかし、トヨタにおいては、「経営」=「トヨタ生産方式(TPM)」の実践であったし、そのTPMは職場組合員の労働負荷に直結するものであったから、経営者が、「口を出してもらいたくない」と思ったとしても、労働組合は言わねばならなかったのである。
梅村氏は「労使相互信頼の原則さえ踏まえれば、労働組合は経営参加ともいえる労使協議を行えばいいし、それをルールとして認めさせることに大きな意義があった」と感慨深い面持ちで私たちに言われた。
だから、労働協約のうちで、この「労使協議会」を定めた条項(第25条)が最重要であったのだ。ここには、経営参加とは記されていないが、「会社と組合が当面する問題について双方の理解を深める」と規定してある。
その実践的意義は、「労働組合は経営が抱える問題に意見を言わせてもらう(双方の理解を深める)。ただし、それを決め、責任を持つのは会社である。」ということである。
これこそが、トヨタ労組にとっての「経営参加」であるというのが、労働協約締結の主導した梅村氏の考えであり、その後のトヨタ労組の基本的考え方となっている。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。