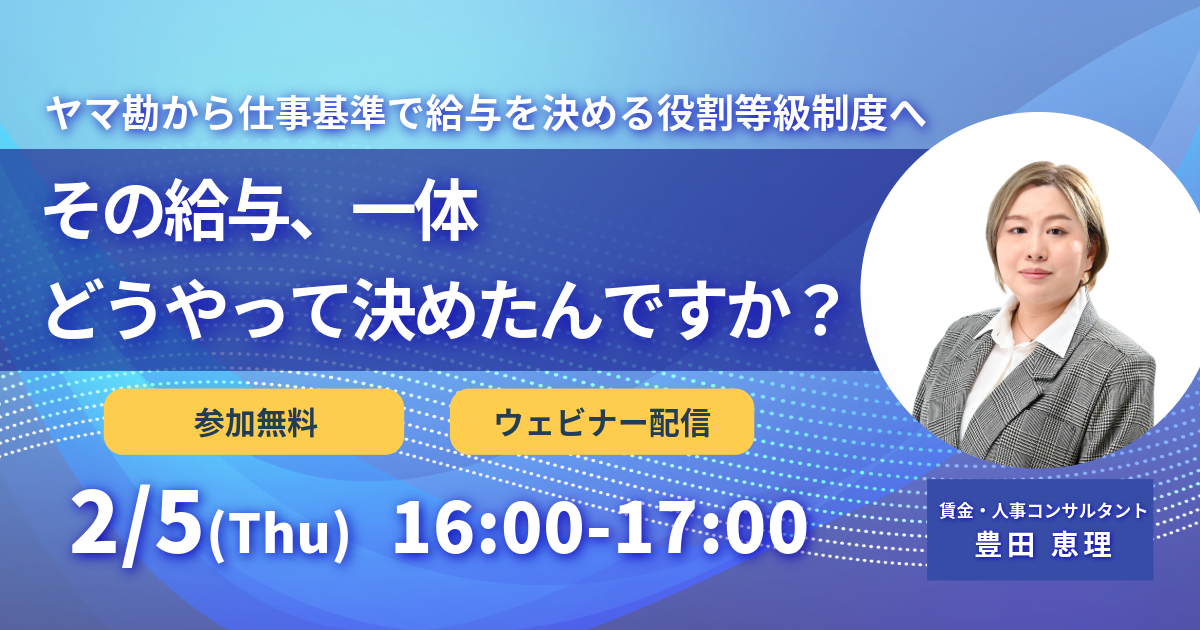なりたい人よりさせたい人

第12回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
強い労働組合とは
労働組合の最大の武器はストライキであると言う人がいる。確かにストライキは会社にとって脅威であるし、一般の人が外から見ても「戦っている」と映る。
しかし、ストライキをやる組合が「強い」か、といえば、必ずしもそうとは言えない。いたずらにストが長引き会社が傾けば組合員の生活は危機に陥る。そんな組合が「強い」とは言えまい。
組合員から頼りにされ、いざという時に「強い団結力」を発揮できる組合こそが「強い」のである。そういう組合は会社にとっても「怖い」存在となれる。
「強い組合」は会社をも強くすると私は考えている。
最近でも頻繁に報道される社内不祥事、品質問題の内部告発などは、きっちりチェック機能を果たせる「強い」労働組合があれば、事件性を持つ前に問題が把握され、解決できていたのではないか。
労働組合の「強さ」は何によってもたらされるのか。私は、結局のところ、そこで運動をリードし、担う労組役員、リーダー達の、人間としての器量、正義感、熱意が「強さ」を支えると考えている。何故なら、労働組合は会社組織のような、組織的パワーがあるわけではないから、運動を考えるのも、引っ張るのも、わずかな人数の組合執行部だからである。
労働組合は組合員のニーズを背景として運動を構築する。また、時には理想を目指し、組合員に必ずしもニーズがなくても組織をまとめその理想を追求しなければならない。そのような運動課題を選択し優先付けして活動にしていくのは組合リーダーである。
だから、労働組合の力量は、リーダー達の力量によってほとんどが決まってしまうといっても過言ではない。したがって、どうやって優れた労組役員を選ぶか、そして選んだ者がふさわしくなければ、どうやって交代してもらうか、その仕組みが非常に重要になる。
労働組合役員が持つ「力」
労働組合役員が持つ「力」というと、一つ思い出すことがある。
私がまだ専従になりたてで、愛知県下の金属関係の労組の勉強会でよく顔を合わせることのあった中堅機械メーカーの委員長の武勇伝的な出来事である。
その会社は、独裁的経営者の下で社員ばかりか、管理者も圧迫され、取締役の一部にも社長交代を画策する動きもあったが、ことごとく潰されていた。
見かねたその委員長が、抜き打ちで記者会見を行い、社長交代の必要性を訴えたのである。その記者会見で委員長は世間を味方につけて、社長を退陣に追い込んだのであった。
委員長も直後に辞任した。その委員長は正義感の強い、バランス感覚のとれた優れたリーダーだと高く評価されていた人だった。
私はこの事件の成り行きを見て、労働組合のリーダーは自分の首をかける気持ちになれば、役員の一人位クビにする力があることを痛感した。
同時に自分にもその力があるのだからと、ある種の「覚悟」が生まれ、すがすがしい気分になったものだ。
しかし、一方でその「力」の使い方を誤れば、委員長が独裁者になる危険があることも感じた。
トヨタ式役員選考方式
労働組合における役員選考はなかなか難しい。多くの労働組合が常に悩んでいる。
私の知るところでは、最も多い選考方式は、現役員が次世代を推薦するという方式である(もちろん最後は組合員による選挙で選ばれる)。
しかし、トヨタでは他にはない変わった役員選考方式が用いられている。少し歴史を振り返ってみよう。
トヨタでは、黎明期から揺籃期にあたる昭和40年初頭までは、以前の稿で触れたように、三役クラスは原則としてほぼ1年交代で代わっていた。
それは、組合結成に集結した多くの多彩な人材が互いに主義主張を戦わせるなかで、巧まずして生まれた方式であった。
初期のトヨタ労組はほぼ同年代の委員長が次々と先頭に立ち労働組合の活力を維持していた。
昭和20年代後半期の組合機関紙を見ると、それまで委員長を担った7人が一堂に集い運動を振り返る座談会の議事録を載せていた。
そこには驚くほどあけっぴろげに鋭い相互批判が交わされていたが、そのざっくばらんさは、アメリカ流のディベートを彷彿とさせるものだった。なるほど、この空気感が誠に自由闊達なトヨタ労組の運動を生み出したのかと理解した。
昭和20年代から30年代は、組合執行部役員は10人程度だった。したがって、誰を選ぶかがすべてだったと初代委員長の江端氏はおっしゃっていた。
そこで、江端氏はOBになってからも、自分で職場を回り、「『一番優秀な奴をくれ』と頼み込んだもんだ。」「でも、結構会社は出してくれたよ」と当時のことを述懐された。会社も組合に優秀な人材が必要であることを心得ていたからだと思われる。
しかし、昭和30年代後半になると、会社も大きくなり、組合員も増え、生産性向上とその分配を勝ち取るという戦略的運動を、会社を向こうに回して貫き、成果を得るためには、次第に運動の継続性が求められるようになる。
また外に向けては全国自動車など産業別運動を担う人材も必要になる。そうした背景から、労使宣言を締結した加藤委員長は2年続投され、それから1期後に委員長になった中根孟氏(中根氏はのちに、トヨタ出身として初めて県会議員となる)は3期3年、続く渡辺武三氏(渡辺氏はトヨタ出身として初めての衆議院議員となる)が4期と、委員長の任期は長くなった。
と同時に組合員数も2万人を超え、支部も増えて、人材を求めるための強い情報源やパイプが必要になってきた。そこで考えられたのが、支部評議会の議長として支部を牛耳っているベテランの職場委員長を巻きこむことだった。
現場の実力者である職場委員長に、役員選考の主力部隊として活躍してもらうため、渡辺委員長の時代に、「議長団」と呼ばれる組織が立ち上がることになる。

やりたい人よりさせたい人
10人余りのボードである議長団の役割は、当初は、職場から優秀な人材を引っ張ってくることであったが、渡辺氏の後に委員長となる梅村氏の時代になると、執行委員の人事の一端を担う重要な存在に発展していく。
この議長団は、年に2回、延べ数カ月にわたり組合に専従し、組合OBや職場、そして、現役の執行委員全員のヒアリングをする。
その中で、この先、長く運動を担ってもらうべき人、下りてもらった方が良い人を選別する。その結果を、執行部の人事の最高責任者である書記長の考えと突き合わせ、人事構想を作る。
そして、執行委員に対し、昇任、異動、職場復帰の辞令を出すのは議長団の団長の役割となる。その宣告には逆らうことはできない。たとえ委員長であっても書記長であっても従わなければならないこととされた。
この仕組みの妙は、職場に根を張る組合員代表に役員人事の骨格部分を委ねることで、組合民主主義にとって最も危険な「独裁者」の出現を阻止できるという点にある。
もちろん労組人事は組合の力の維持にとって要諦をなすから、時の三役とりわけ書記長との息は当然合わせなければならない。
しかし、人事責任者の書記長でさえも、議長団との徹底対立は許されない。10数名からなる職場代表の見識は、最大限重んじなければならない。ただ、議長団は職場代表であり、連合や産別といった外部の事情などは分からないから、外部派遣者の人事は委員長や書記長の考え方が尊重される。
そうであっても「表に出るのはあくまで議長団」というところが「自由闊達に話し合って決める」「トヨタらしさ」を維持できている秘訣なのだ。
そういうことであるから、トヨタにおいて、この仕組みに逆らって独裁を振るうことは不可能である。
この絶妙の人事を、執行委員全員に戒めるため、トヨタ労組では、全員に対し、常に、「やりたい人より、させたい人」しか役員にはなれない、というわかりやすい言葉で意識を徹底している。
この言葉が生きている限り、トヨタには、自分のために運動を振り回すような独裁者は現れない。それは、組合が健全であり続けるため、トヨタ労組が生み出した知恵である。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。