外国人の入社手続きにおける留意事項

第99回ホワイト企業の人事労務ワンポイント解説
Q
当社は中小企業ですが、人材採用難のため外国人労働者の雇用を計画しています。採用にあたって慌てないよう、日本人を雇用する場合との違いなど、人事総務担当者が心得ておくべき基本事項を教えてください。
A
我が国で働く外国人労働者数は、厚生労働省の「令和6年外国人雇用状況の届出状況」によると、令和6年10月末時点で2,302,587人となり、3年前の同月末(1,727,221人)と比べて約33%増加しています。
また、外国人を雇用する事業所数も34万事業所に達し、前年から2万事業所以上増加しています。本稿では、このような外国人労働者の増加を踏まえ、雇用にあたっての入社手続きに関する留意点を解説します。
採用前・採用時の注意事項
採用にあたって、外国人労働者が日本人と異なるのは、入国時などに許可された「在留資格」の範囲内でしか働けないという点です。そのため、企業としてはまず在留資格を確認することが重要となります。就労予定の業務がその在留資格の範囲に含まれているか、また在留期限が切れていないかなどを確認する必要があります。なお、特別永住者(在日韓国人・在日台湾人など)は在留活動に制限はなく、日本人と同様に就労することができます。
確認の際には、在留カードまたは特別永住者証明書の現物を確認することが重要です。在留カードが偽造・変造でないことの確認のためには出入国在留管理庁のWebサイトで番号を照合したり、無料公開されているアプリなどを利用して確認することが可能です。
在留資格には期限があるため、雇入れ後も本人任せにせず、会社が期限や更新状況を管理することが重要です。在留資格外の業務をさせたり、期限切れで就労資格のない者を働かせると、会社は「不法就労助長罪」に問われる恐れがあります。
採用が決まったら、労働基準法15条に基づき、労働条件を明示した雇用契約書・労働条件通知書を交付する必要があります。その際、外国籍従業員については、労働契約期間にかかわらず、例えば「労働契約は、就労可能な在留期間が満了し、更新が認められなかった場合には、その満了をもって終了する」といった条項を明記しておきましょう。
労働条件通知書や就業規則を外国人労働者の母国語で作成する義務はありませんが、理解できない内容を示しても意味がありません。労働条件通知書については、厚生労働省が外国人労働者向けにモデル様式を公表しているのでこれらを活用するとよいでしょう(現在、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語が用意されています)。なお、性別や国籍を理由に待遇や労働条件を区別することは禁止されているため、内容の異なる外国人専用の就業規則を別途作成することは避けるべきです。母国語で翻訳した資料や、平易な日本語による補足を用いて就業規則の内容を理解させるようにします。
また、安全衛生教育も重要です。不慣れな作業で説明が不十分なまま重大な労災事故が発生すれば、会社は安全配慮義務違反を問われかねません。厚生労働省から、「安全衛生教育は、母国語を用いる、視聴覚教材を使用する等、外国人労働者が理解できる方法で行うこと」とする告示が出されています。
社会保険の資格取得
社会保険については、外国人労働者も日本人を採用する場合の資格取得手続きと基本的に違いはありません。
ただし、外国人の場合には「氏名とフリガナ」、および通称名の取扱いが問題となります。在留カードには氏名がローマ字で記載されており、フリガナはありませんが、社会保険の手続きではカタカナのフリガナが必要です。例えば「王」さんの場合は「オウ」か「ワン」か、「Michael」さんは「マイケル」か「ミヒャエル」かなど、本人に確認が必要になります。
しかし、本来、外国籍の方の名前にカタカナ表記があるわけではないため、フリガナを記載した住民票(自治体による)や、住民票に表記がない場合でも自治体での登録内容を確認したうえで手続きを行うことが望ましいでしょう。また、住民票に漢字・ひらがな・カタカナの通称名が登録されており、本人が希望する場合には、通称名で資格取得することが可能です。
外国籍の被扶養者登録については、氏名と国外居住に関する点に注意が必要です。外国籍に限りませんが、被扶養者の追加申請があった場合には、住民票や戸籍謄本を提出してもらい、続柄を確認する必要があります。外国籍の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合、フリガナの取扱いは被保険者資格の取得時と同様に注意が必要です。さらに、令和2年4月の改正により、健康保険の被扶養者要件として「日本国内に住所を有すること」が追加されました。そのため、原則として海外に生活基盤を置く家族を被扶養者とすることはできません。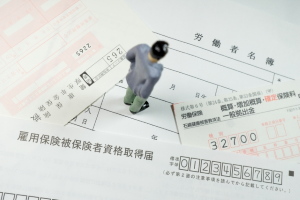
雇用保険の資格取得
外国籍の人を雇い入れたり離職させたりする際には、雇用保険に入らない短時間労働者であっても、雇用形態にかかわらずハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります(特別永住者および在留資格が「外交」「公用」の場合を除く)。雇用保険の被保険者資格を取得・喪失する場合には、資格取得(または喪失)届の所定欄にローマ字氏名、国籍、在留期限、在留資格、在留カード番号などを記入することで、外国人雇用状況の届出を兼ねることができます。
手続きにあたって注意すべき点として、通称名で生活している外国籍の方を日本人と思い込んで処理してしまうケースが考えられます。住民票やマイナンバーカードには本名と通称名が併記されているため、必ず外国籍かどうかを確認することが大切です。
また、雇用保険の届出の際には氏名とフリガナを住民票どおりに記載することが重要です。外国人労働者も失業給付や育児休業給付を受給することが多いですが、フリガナが異なると振込ができないケースが発生するため、市区町村での登録内容を確認し、銀行口座のフリガナと一致させておくことが大切です。
今後、外国人労働者の採用は一層増加することが見込まれます。人事・総務担当者は、採用が発生した際に迅速かつ適切に対応できるよう、必要な手続きや体制をあらかじめ整えておくことが求められます。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。

