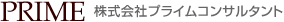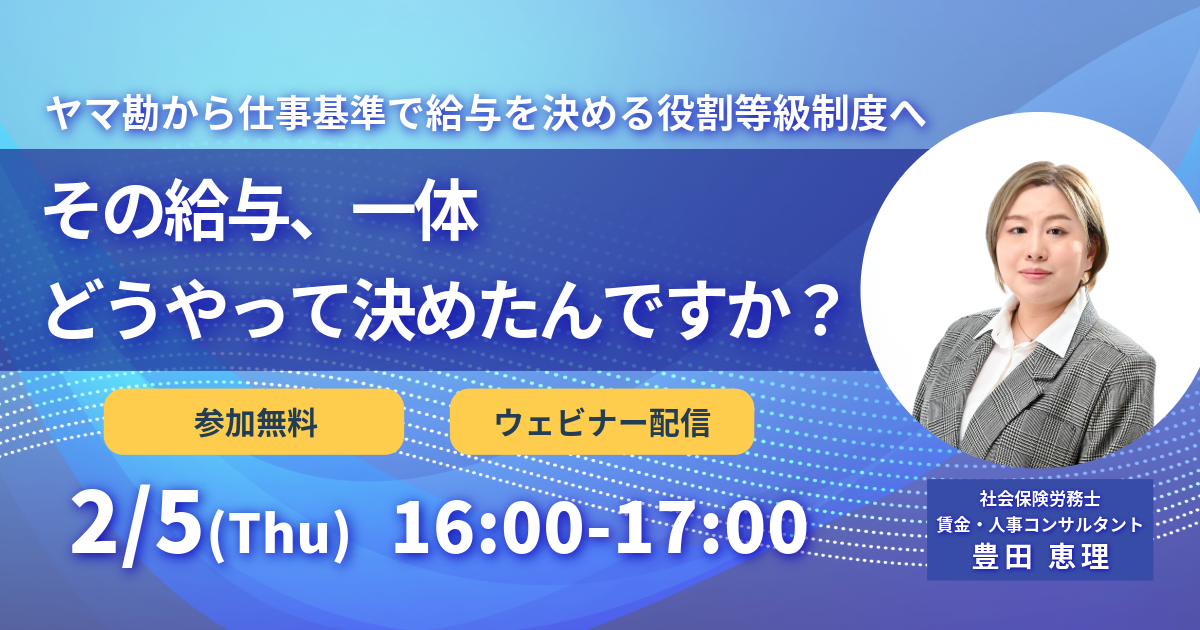労使対等は形から

第9回 労使はこうしてトヨタをつくりあげた
「車の両輪」の実現
労働組合と会社とは、会社業績を上げることについては運命共同体となれる。しかし、その成果を分配する段になると労使の利害は対立する。
パイの取り合いであるから、本来対立するものではあるが、トヨタにおいては、その時々の分配を長期的に積み重ねたとき、労働者の生活安定と企業の経営基盤の両者が「車の両輪」のごとくバランスがとれていれば良い、と考える。これが、労使宣言が目指す理想の姿である。
トヨタにおいては、個々の交渉事が、その目指す範囲内で決着できたかどうか、それを判断する指標は、結果そのものでなく、そのプロセスで互いに精一杯の主張ができたかどうかで判断する。
交渉である以上、要求決定の段階から妥結まで100%満足ということはありえない。トヨタでは一時金(ボーナス)の回答は「満額」ということがよくあるが、それなら組合にとって100%だろうというとそうではない。
何故なら、要求決定の段階から、労働組合は、長期的に見て「車の両輪」が成立するぎりぎりの水準を「徹底した議論」の末に見出しているからである。
それは業績だけから見れば抑制的であることも多いから、職場組合員から見れば決して全員が「満足」ではなく、あくまでも「納得」した水準でしかないということなのだ。
私がトヨタ労組に在籍した8年間で、賃金から福利厚生など百近い項目の交渉事を決着させてきたが、会社回答に100%満足できたことはほとんどない。自分でぎりぎり「納得」できたから職場に「妥結提案」した、というものばかりであった。
トヨタ労組中興の祖である梅村志郎氏は、そういうトヨタの妥結水準を、「うちの会社は絶対100点なんか取らせてくれん。大体80点くらいの合格水準を出してくるから、まあ納得するしかないんだな」と言っていた。
「納得」水準の判断基準
労働組合として、この微妙ともいえる納得水準を見出せるか出せないか、それは、「徹底した話し合い」ができていたかいなかったかで判断するしかない。労使関係ではそれがベストだとトヨタ労使は考えてきた。
なぜなら、経済の行方に「絶対」などないから、長期的な先行きを現状で100%言い当てることはできないが、労使相互信頼の考え方の下で、互いに英知を振り絞って、徹底的に話し合った結果、到達した水準ならば、その時における「最適水準」であるはずだと労使が考えているからである。
なぜ、そのような抽象論で納得できるのかというと、トヨタ労使の交渉は常に「対等」な立場にあるもの同士が、徹底して話し合っているのだから、そこで見出された結論は少なくとも当事者である労使にとって、これ以上も以下もないはずだと受け止めているからである。
「労使対等」を担保するもの
労使交渉で議論になるのは、会社が置かれた状況をどう見るか、そして組合要求への回答水準が経営の先行きにどのような影響を与えるのか、また、そうした背景で、どのような水準であれば組合員は納得してくれるか、ということである。
交渉では、組合としては、経済的な背景から始めて、その要求が組合員の総意によるものであり、それに会社が答えることで組合員のモチベーションがどれだけ上がるか、ということなどを最大限訴える。
しかし、もともと会社経営に関する諸データは、会社が持っているものの方が質量ともに圧倒的に上である。
バックについているスタッフの数から見ても、会社は組合を圧倒している。したがって、議論の土俵でははじめから経営側が頭一つ高く、組合は相当背伸びして勝負することになる。
そういう中でも、トヨタが「労使対等」という、一種の共同幻想を、現実にあるかの如く信じ、そこから出てくる結論に納得できるのは、話し合いの場が、対等であるという「形式」がきっちり守られていることによる。
トヨタでは、春闘交渉における団交を「労使協議会」と呼び、期間中5回程度行う。
この参加者について、労働協約には「同人数で行う」ということしか書いてない。しかし実際は「労使宣言」以降、会社は必ず社長以下全役員と部門代表、労働組合は委員長以下全執行委員と、職場委員長が出席する。
私が書記長の頃でも、両者合わせて350人くらいの出席者であった。ここでは、交渉のまとめで、会社は社長、組合は委員長が結ぶ(もちろん、実際の水準交渉はこのような大勢の場でなく、組合三役対会社労務担当役員による縮小折衝の場で詰められる。この辺りは後に詳述する)。
ここでは、会社が社長、組合は委員長を最高責任者として協議したという「形」が重んじられているのだ。そして、社長も委員長も自分達の組織の責任ある者全員を率いて、この交渉で対峙している。
この対等性は、絶対の原則である。トヨタにおいては、大から小まであらゆる交渉は、労使とも同等の「位」に位置する者によって行われてきた。

労使対等は「位」の対等性で担保される
トヨタでは、代々、現場部門から委員長と副委員長1名を選び、管理部門いわゆるホワイトカラーから書記長、副委員長2名を選んでいる(この構成は、労使宣言以降、厳守されている)。
組織上はこの下に、支部長、スタッフ局の局長、部長を設置し、執行部を構成している。
交渉で会社と対峙するのは、執行部であるが、私たちは、交渉相手の「位」の対等性を極めて重視してきた。
委員長のカウンターパートは社長。書記長、副委員長の場合は、担当役員もしくは部門長。局長は部長。部長は課長クラスに対応すると理解してきた。梅村氏からは「部長は係長以下の人間とは絶対に交渉してはいかん」と強く指導された。
なぜなら、6万組合員の生活をかけて交渉する執行部側が、会社においてそれ相応の責任を負っている相手と交渉しなかったら、組合員を代表する使命は果たせないからである。
会社組織は組合以上にヒエラルキーに縛られているから、狭い責任しか負わない下級管理職の価値判断では大局観に立った議論はできないと考えるからである。交渉時には、その交渉事を担当するセクション全体の職掌に首がかかっている人と対峙する必要があるのだ。
そして、もう一つの理由は、限られた専従期間、労働組合に派遣されてくる執行委員が、短期間に組合員全員を代表しているという使命感を持たせるには、まずはカウンターパートとなる会社側の役職に対応する責任を負っていると自覚するのが近道であるからである。
例えて言えば、トヨタでは書記長は管理部門出身であるから、大変若くして、その職を担うことになる。職場では係長もしたことのない者が、組合で書記長に抜擢され、その交渉相手は担当役員となる。
つまり、30代半ばの若造がいきなり4階級上の50歳代の役員と、「対等」に渡り合うというようなことになる。
私も36歳で書記長になったが、その地位の重さに身が震える思いがしたものだ。
しかし、一方では、大きなやりがいも感じた。責任を果たすためには、高下駄をはいて、さらに背伸びをしてでも、「対等」を具現化しなければと気負っていた。
会社から、交渉事で、課長クラスが接触してきても、「役員とでなければ話はしないよ」と言い放ったものだ。そして、ありがたいことに、会社もそれを正面から受け止め、組合でのポストを最大限尊重してくれたことだ。
私が書記長の頃の労務担当役員は磯村巌氏だったが、磯村氏は、交渉ではない場、例えば社内運動会の会場で仲間に混じって行き会ったときでも、絶対に私を「加藤君」とは呼ばなかった。「加藤書記長」とか「書記長」とか呼んで、礼を尽くしてくれたものだ。
ことほど左様に、「対等」は大事な原則なのだ。そうでなければ、現場の組長クラスであった支部長がいきなり役員である工場長と対等に口をきくことなどできない。
しかし、この形を取り続けていることが、労使間の交渉力の差を補完し、徹底した話し合いを可能とする基盤を維持してきたのだ。
トヨタでは、このように労使対等を「形」で担保することで、「労使相互信頼」という、目に見えない価値観を「見える化」しているのだ。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。