改正旅費法の概要と旅費規程の見直しについて

第96回ホワイト企業の人事労務ワンポイント解説
Q
宿泊費などの上昇により、ごく平均的なホテルを利用した場合でも、当社の旅費規程で定めた出張費の範囲を超えてしまうケースが頻発しています。
出張者が不利益とならないように、申請に基づく差額の調整を行っていますが、例外対応が増えたことで総務部門の事務負担が大きくなっています。
旅費規程を現状に即した内容に見直す場合、どのような方法・手順を取るのが適切でしょうか?
A
コロナ禍の沈静化以降、物価の上昇や急激な為替変動に加え、都市部のホテル代の高騰などにより、従来の会社の旅費規程では実態にそぐわないケースが急増しています。
本稿では、令和6年に成立し、令和7年4月に施行された「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律」(以下「旅費法」)の概要を紹介し、民間企業の旅費規程において参考となりうるポイントを取り上げます。
なお、旅費法には海外渡航や赴任に伴う転居費に関する規定もありますが、スペースの関係で国内の宿泊を伴う出張に限定して検討します。
国家公務員等の旅費法の改正項目
旅費法の改正項目の中から、宿泊費、日当、交通費について以下、見ていきましょう。
(1)宿泊費…定額支給から実費支給に変更
今回の改正で最も大きな変更が、宿泊費の扱いです。従前の旅費法では、事務の簡素化などの理由から宿泊費を「定額支給」としていました。たとえば、「係長・課長補佐級が東京や大阪などの都市部で1泊したときの宿泊費(夕朝食代込み)は1万900円、都市部を除いた地方は9800円」となっていました。しかし、インバウンド需要の増大やダイナミックプライシング(需要に応じて価格が変動する仕組み)が進んだことで都市部のホテル宿泊費が急騰し、定額の範囲内では宿泊できない状況が続出しました。
このため、今回の改正では「実費方式」へと大きく変更されました。実費支給への変更に伴い、不必要な華美なホテルの利用を抑制するために、上限付きの設定としています。
(2)日当…昼食代を廃止し、宿泊手当に切り替え
改正前の日当は、昼食代を含む諸雑費および目的地を巡回するための交通費(バス等)を補う旅費とされていました。このうち、昼食代については、通常の勤務時でも必要となる費用のため支給しないことに改められました。改正前の日当は、昼食代を含む諸雑費および目的地を巡回するための交通費(バス等)を補う旅費とされていました。このうち、昼食代については、通常の勤務時でも必要となる費用のため支給しないことに改められました。
他方、宿泊出張の場合は通常の勤務時と比べ諸雑費(夕朝食代がかさむ費用等を含む)が発生するため、日当を廃止し定額の宿泊手当を支給することに変更されました。国内の場合の宿泊手当は地域に無関係に1夜2,400円ですが、宿泊費に夕朝食代が含まれている場合もあるので、その調整事項も規定されています(宿泊費に朝食または夕食が含まれている場合は宿泊手当が2/3に減額され1,600円支給、夕朝食の両方が含まれる場合は宿泊手当が1/3に減額され800円支給、等)。
(3)交通費…車賃を廃止し自宅発出張も可
出張のために要する交通費は、これまでも実費弁償が基本でした。しかし、旅費法制定当時は民間のバス等の運賃や経路確認、交通機関の利用証明が困難といった事情がありました。そのため、これまでは「1Kmあたり37円」と定められていた「車賃(バス・路面電車等)」が支給されたりしていましたが、新制度では廃止され、実費支給となりました。
また、従前は「官署を出発地とする」というルールが基本でしたが改正法では自宅発の出張にかかる旅費の支給申請が可能になりました。さらに、「特急券は片道100Km以上」とされていましたが、今や交通網が発達し、短距離でも特急利用が当たり前になっていて、この旧ルールが廃止されました。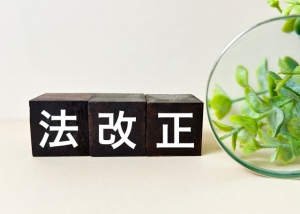
民間企業の旅費規程の見直し
以上の改正旅費法は国家公務員向けの規定ですが、これまでも「出張手当」や実費精算のルール策定を、「国の制度を参考にしている」とする企業は多かったといえます。そこで、今回の旅費法の改正に伴い、民間企業における旅費規程の見直しについて考察します。
(1)国内宿泊費
民間企業において、宿泊料の支給方法については実費支給(上限付き)が67.7%、定額支給が28.9%という調査データがあります(財務省の令和5年調査)。
今回の旅費法の改正を踏まえ、定額支給としている企業においても、上限付き実費支給に変更する企業が増えることが想定されます。
その場合、実費支給を前提にしつつ、1泊の上限金額については、例えば、役員3万円、部課長2.5万円、一般職1.5万円といったように職責の重さに応じて定める方法が考えられます。また、宿泊地域毎にホテル代が大きく異なる状況が想定されますが、改正旅費法の別表第2に都道府県毎の宿泊費基準額が定められているので、これらの金額を参考にすると良いでしょう。一例として、東京都内の場合、1夜につき内閣総理大臣等が4万円、指定職職員等が2.7万円、職務の級が10級以下の者が1.9万円となっています。
(2)日当または宿泊手当
日当の見直しについては、改正旅費法が参考になると考えます。すなわち、昼食代は支給対象外とし、1夜の宿泊に伴い夕朝食費等の出費がかさむことへの補填として2,400円程度を支給する。また、宿泊費に夕朝食代が含まれている場合や自宅(またはこれに相当する場所)に宿泊する場合の調整などを定めると良いでしょう。
(3)交通費
交通費については、現在でも実費支給がほとんどだと思います。ただし、実費支給とした場合でも、交通機関の種類(鉄道、船、航空機など)や新幹線や特急、グリーン車などのランク等を自由に選択させることは不必要な利用を誘発しますので、職責の重さなどを考慮の上、利用条件等を明確に規定すると良いでしょう。
不利益変更の問題
就業規則の不利益変更に相当する場合の考え方としては、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情に照らして、変更に合理性が認められるかが判断基準となります(労働契約法10条)。
旅費法の改正に伴う労働条件の見直しであれば、②労働条件の変更の必要性、③内容の相当性は肯定されやすいと考えられます。あわせて、必要に応じて経過措置を設けるなどの配慮も有効です。
現行の会社の旅費規程が実情に合っていないと感じている企業は少なくないと思います。今回の旅費法改正は国家公務員を対象としたものですが、民間企業にとっても規程を見直す良い機会といえます。これを参考に、自社の実情に即した改善を検討されてはいかがでしょうか。
プライムコンサルタントでは、本記事のようにWEB会員限定サービスをご提供しています。
「WEB会員」サービスはどなたでも無料でご利用いただけます。
今すぐご登録ください(入会金・会費など一切無料です。また、ご不要であればいつでも退会できます)。

