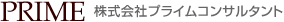ブラック企業問題と企業を取り巻く環境の変化ー7ー

ブラック企業問題と企業を取り巻く環境の変化(7)
皆さんこんにちは。コンサルタント・社会保険労務士の津留慶幸です。
前回、「サービス残業問題」への間違った対応事例として、次の5つの例について解説しました。
i)残業代は支払うが、残業時間に上限を設けておき、上限を超える時間の申告を認めない
ii)「みなし労働時間制」を、本来適用できない人にも適用する
iii)従業員の大半を管理職として扱う
iv)年俸制を導入して残業代を支払わない
v)現在の賃金総額の中に固定残業代100時間分を含んでいることにする
中でも、「みなし労働時間制」や「固定残業代」の運用には間違いが多く、裁判にまで発展した事例も少なくありません。
「みなし労働時間制」については、当社ホームページで連載中の「中川恒彦の人事労務相談コーナー」の第95回、第96回で、詳しく解説していますので、今回は「固定残業代」について考えていきたいと思います。
3.サービス残業問題
(6)固定残業代に関する裁判例
固定残業代(定額残業代、固定時間外手当など名称はさまざま)とは、一般的に、残業時間に関わらず一定の金額を残業代として支払うという制度です(制度と言っても、法律で規定されているわけでなく、実務の現場で広まっていった払い方の一つです)。
前々回(第5回)にも少し触れましたが、「実際の残業時間に関係なく、一定の金額を支払っていればそれでよい」という制度ではありません。
実際に残業した時間を基に計算した残業代が固定残業代の額を超えている場合は、その差額(超過分)を支払う必要があります。
このこと自体は数多くの裁判例で示されており、「中川恒彦の人事労務相談コーナー」の第5回、第6回、第7回では複数の裁判例を詳しく紹介しています。
過去の裁判を見ても会社側が敗訴した例が多く、固定残業代の設定・導入には十分に気を付けなければならないことは以前から変わりありません。
しかも、最近はさらに会社側に厳しい判決が見られるようになってきています。
ここからは、具体的な裁判例を紹介し、現在、固定残業代についてどのような判断が下されているのかを見ていきたいと思います。
【テックジャパン事件】(平成24年3月8日 最高裁)
<概要>
月の所定労働時間が160時間の会社において、会社は従業員Aと次のような契約を結んでいた。
・月間総労働時間が140時間~180時間の場合には基本給41万円を支払う。
・180時間を超えた場合は、さらに1時間当たり2,560円の残業代を支払う。
・ただし、140時間に満たない場合は、1時間当たり2,920円を控除する。
従業員Aは退職後に割増賃金の支払いを求めて訴えを起こしたが、会社側は41万円の中に180時間までの割増賃金は含まれていたと主張。
東京高裁は会社側の主張を認めたが、最高裁は、
・残業しても「基本給」は増額されない。
・「基本給」のどの部分が通常の労働時間分で、どの部分が割増賃金に当たるのか判別できない。
ことを理由として会社側の主張を認めず、高裁に差し戻した。
またこのとき、最高裁の櫻井裁判官は「補足意見」として、次のように述べている。
固定残業代として一定時間分の残業代が支払われている場合、
・その旨(例えば10時間分の残業代として支払っていること)が雇用契約上明確でなければならない。
・給与支給時に固定残業代の金額と対象時間数が従業員に明示されていなければならない。
・一定時間を超えて残業した分については、別途、差額を支払う旨をあらかじめ明らかにしておかなければならない。
・本件の場合は、そのようなあらかじめの合意も支給実態も認められない。
この裁判は、判決そのものよりも、櫻井裁判官の「補足意見」に大きなインパクトがあり、その後の裁判に大きな影響を与えています。
それまでにも、固定残業代の要件を示す裁判はありましたが、「通常の労働時間に対する賃金と残業代に当たる部分が判別できるようにすること」と述べるにとどまり、「補足意見」のように、
・一定時間分の固定残業代を支払っていることを契約上明確にすること
・給与支給時に、固定残業代の金額と時間数を明示すること
までは言及されていませんでした。
さらに、今回の「補足意見」は、
・一定時間分を超えて残業した場合の差額分支払いの「合意」、「支給実態」
についても指摘されており、これらの要件を満たさないものは「固定残業代とは認められない」=固定残業代も残業代の算定基礎に含めて計算した残業代の支払いを命じられる恐れがある、ということになります。
実際にこの判決以降、同様の判断が示される裁判は増えていますので2つの裁判例をご紹介したいと思います。
【アクティリンク事件】(平成24年8月28日 東京地裁)
<概要>
会社は営業担当の従業員に対して、月30時間分の営業手当を支払っており、営業手当は固定残業代としての性格を有することが賃金規程に規定されていた。
しかし、
・営業手当は顧客との面談の際の諸経費を賄う趣旨も含んでいた(残業の対価としての賃金とは言えない)ことや、
・実際の残業時間との差分(超過分)については支払っていなかった
ことから、この営業手当は固定残業代とは言えないと判断され、営業手当を残業代の算定基礎に含めて残業代を計算することが求められた。
この裁判では、賃金規程に営業手当が残業代に相当すると定められていたにも関わらず、「超過分の支払い」がなかったことから、固定残業代とは認められませんでした。
会社側は30時間分については残業代を支払っていると認めてもらい、負担増は超過分の支払いだけにとどめてもらえると期待していたかもしれませんが、それを覆す厳しい判決となっています。
【木下工務店事件】(平成25年6月26日 東京地裁)
<概要>
基本給および調整給の60%を本給(所定労働時間の賃金)、残り40%を残業、深夜勤務、休日勤務の手当とする旨を賃金規程に規定しており、従業員への労働条件通知書にも明記されていた。
訴えを起こした従業員に対して会社側は、給与のうち40%が85時間分の残業代だったと主張。
しかし、
・40%には深夜勤務や休日勤務分の割増賃金も含むことになっており、40%が残業何時間分に当たるかは毎月変動する。
・よって、残業何時間分に当たるのか確定することができない。
・また、60時間超の割増(5割)も考慮されていない。
ことから、この規定や契約内容は無効とされた。
予め賃金規程や労働条件通知書に明記していたにもかかわらず、割増賃金としての性質が認められなかった判決です。
否認の理由は、「割増賃金の詳しい内訳」が事前に示されていなかったことです。
60時間以下の残業と60時間超の残業(※)、深夜勤務、休日勤務ではそれぞれ割増率が異なります(※中小企業は60時間以下と60時間超は同じ割増率でも可)。
そのため、それら全てを1つの手当(固定残業代)に含めた場合、それぞれ何時間分が入っているか、つまり「割増賃金の詳しい内訳」が判別できず、固定残業代としての要件を欠いてしまったのです。
このケースで、もし、どうしても固定的な支払いをしたいなら、「残業代○円・○時間、深夜勤務△円・△時間・・・」のように、残業、深夜勤務、休日勤務のそれぞれについて金額と時間数を定めておかねばなりませんが、そこまでして固定的に支払う意味はあまりないように思います。
ここまで、固定残業代に関して、比較的新しい3つの裁判例をご紹介しました。
いずれも、単純な残業代の未払いではなく、「会社としては残業代のつもりで払っていた賃金が全く残業代とは認められない」という、会社にとって非常に厳しい判断が下されています。
「固定残業代」を導入している中小企業は少なくないと思いますが、規定の仕方や運用方法を間違うと、想像をはるかに超える多額の支払い命令が下され、組織的にも経営的にも大きな打撃を被ることになりかねません。
ときどき、「残業代を抑制するために固定残業代にしようか」という声を聞きますが、コスト削減という目的ではお奨めできません。
支払う残業代が減る根拠がないからです。
繰り返しになりますが、固定残業代は、みなし残業代のように「残業代を固定」するものではありません。
実際の残業が固定残業代を上回った部分は別途支払う必要があります。
一方で、実際の残業が固定残業代を下回っても減額しないというという支払い方です。
残業が想定より少なくても固定額を払い、想定を超えたら固定額に上乗せするわけですから、支払う残業代が少なくていいことはあり得ず、逆に、残業代払いが増える可能性が大です。
その上、社員への事前周知、規程類の整備、運用時の明細の明記といった多大な運用コスト、さらには運用方法について疑義を唱えられるリスクもあります。
もしも固定残業代の導入を検討される場合は、これらのデメリットやリスクをしっかりと勘案した上で、慎重に判断することが大事です。
プライムコンサルタントの
コンサルティング
コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?
当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。
これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。
担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。
会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。
人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。