Unit 5: 日本の女性雇用の現状と課題-駆け出しコンサルタントの学習成長ブログ(人事管理・労働経済編)

前回は、「職場におけるメンタルヘルス対策とうつ病」について学習しました。
今回は、「日本の女性雇用の現状と課題」と題し、労働力率の推移とM字カーブの変化の理由等について見ていきます。また、管理職に占める女性割合や賃金格差の国際比較データを用いて、女性雇用に関する日本と諸外国の違いを明らかにしていきます。
1.日本の女性雇用の現状
①年齢階級別労働力率の推移とM字カーブ
今回は、女性雇用の現状と課題について学習します。突然ですが、日本の女性雇用の特徴を表す「M字カーブ」という言葉を知っていますか?
はい。確か、労働力率をグラフにするとM字を描くことから、そのように呼ばれていると記憶しています。
その通りです。正確には、女性の労働力率※を年齢階級別にグラフ化した際に描かれる、アルファベットのMの形状に似た曲線のことを、M字カーブと言います。どのようなものなのか、次の図表1で確認してみましょう。
※労働力率(%)=労働力人口/15歳以上人口×100
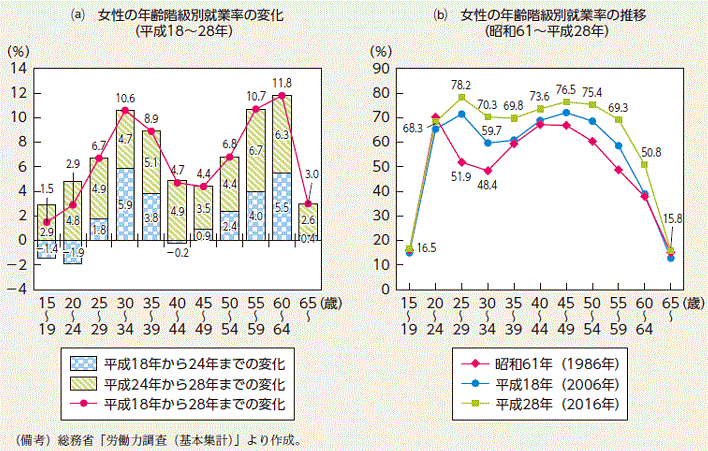
資料:内閣府「男女共同参画白書 平成29年版」
M字カーブは、20代で学校を卒業して就職し、30代で出産・育児に専念するため仕事から離れ、子育てが落ち着いた40代で再び労働市場に戻ってくるという日本女性の働き方の特徴を表しています。
時系列で見ると、M字カーブの底が浅くなるとともに、勾配が緩やかになっているのが分かります。これは、何を意味するのでしょうか?
M字カーブの底が浅くなっているのは、全体的に働く女性の割合が増えてきていることを表します。勾配が緩やかになっているのは、30代で仕事から離れる女性が以前より減少したことを意味します。その理由は、育児休業など企業側の制度整備が進んできたことや、男性と同じ労働条件で長く働くことを望む女性が増えてきたことなどが考えられます。
なるほど。これまで、出産・育児を機に退職を余儀なくされていた女性が、その後も働き続けられる環境が整備されてきた等により、労働力率が上昇してきたのですね。ところで、国際的な観点から女性の就業を捉えた場合、日本の女性雇用はどのような状況にあるのでしょうか?
②女性の就業率の国際比較
前述の通り、女性の就業率は年々高まっています。25~54歳の女性の就業率をOECD諸国と比較すると、その数値は決して高いとは言えませんが、国際平均と見劣りしない水準だと言えます。次に示す図表2で具体的に確認してみましょう。
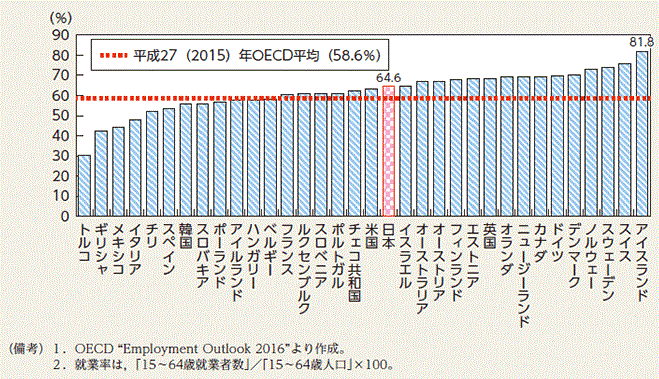
資料:内閣府「男女共同参画白書 平成29年版」
ここでは日本は34か国中16位で、イスラエルの次に位置しているのですね。就業率81.8%でトップのアイスランドには及びませんが、日本は64.6%でOECE平均の58.6%を上回っていますから、女性の労働参加が進んでいる国として多少の自信を持ってよいかもしれませんね。
確かに、25~54歳の女性の就業率で言えば国際平均と肩を並べる水準ではあります。しかし、その就業の内容や実態を見てみると、諸外国と比較して劣っている部分が大きく2つあります。
国際比較で見劣りする2つとはどのようなものなのでしょうか?具体的に教えてください。
1つは、管理職に占める女性割合です。もう1つは、男女間の賃金格差です。
言われてみれば、昨今報道でもそのような話題が取り上げられています。それらに関する具体的な統計やデータ等があれば教えてください。
③役員・管理職に占める女性の割合
次に示す図表3のとおり、日本の管理的職業従事者に占める女性の割合は、2016年では13.0%であり、諸外国と比べて低い水準となっています。
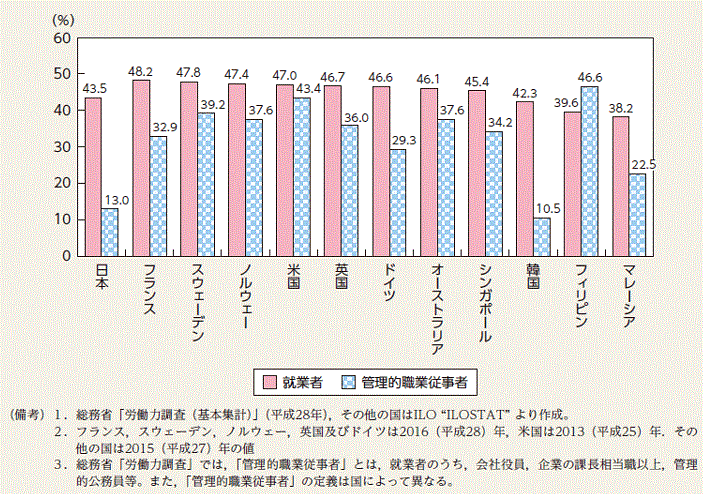
資料:内閣府「男女共同参画白書 平成29年版」
確かに、諸外国と大きな開きがあることが分かります。米国と比較すると、女性の就業者割合では大差ないにもかかわらず、管理職割合は日本の約3.3倍の43.4%となっています。このままではいけないと思いますが、女性の管理職割合を高める取り組み等は何かなされているのでしょうか?
政府は、2020年までに管理職に占める女性の割合を30%とすることを目標に掲げており、2016年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」を施行しました。この法律では、301人以上※の社員を雇用する企業に対して、女性の活躍推進に向けた行動計画を策定することなどを義務付けています。
※300人以下の企業は努力義務
この法律では、行動計画を策定・届出し、かつ女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができるようになっていますね。通称「えるぼし認定」※と呼ばれ、認定を受けた企業のみが使用できる「えるぼし認定マーク」を自社のホームページに掲載すれば、女性が活躍できる企業として採用のPR材料等として使えますね。
※「えるぼし」は労働(Labor)と女性(Lady)の頭文字Lと、星のように輝く女性のイメージを表します
④男女間の賃金格差
次に、男女間の賃金格差に関するデータを図表4に示します。ここでは、正規従業員である男女フルタイム社員の中位所得の差を国際比較しています。男性の賃金を100%とした場合の男女賃金格差は、日本は25.9%となっています。韓国、エストニアに次いでOECE加盟国中3番目に大きいのです。
| (単位:%) | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2013年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルギー | 13.6 | 11.5 | 7.0 | 5.9 | 3.3 |
| ニュージーランド | 7.2 | 9.6 | 7.0 | 6.6 | 6.1 |
| デンマーク | - | 10.2 | 8.9 | 6.8 | 6.3 |
| フランス | - | - | 9.1 | - | 9.9 |
| スウェーデン | 15.5 | 14.4 | 14.3 | 13.4 | - |
| オーストラリア | 17.2 | 15.8 | 14.0 | 18.0 | 15.4 |
| イギリス | 26.3 | 22.1 | 19.2 | 17.5 | 17.4 |
| ドイツ | 19.6 | 16.3 | 16.7 | 14.1 | 17.4 |
| アメリカ | 23.1 | 19.1 | 18.8 | 17.9 | 17.5 |
| カナダ | 23.9 | 21.3 | 19.0 | 19.3 | 19.2 |
| フィンランド | 20.4 | 18.9 | 18.9 | 20.2 | 19.6 |
| 日本 | 33.9 | 32.8 | 28.7 | 26.6 | 25.9 |
| エストニア | - | - | 27.8 | - | 28.3 |
| 韓国 | 41.7 | 39.6 | 39.6 | 36.6 | 36.7 |
資料:OECD Data「Gender wage gap」より作成(2018年4月現在)
時系列で見ると年々解消してきてはいますが、ベルギーやニュージーランドの数%と比較すると、日本の男女間賃金にはまだ大きな格差があるのですね。しかし、同じ正規従業員なのに、なぜこのような男女賃金格差が生じているのでしょうか?主な原因があれば教えてください。
主な原因として、①勤続年数、②職階の違いが男女間賃金格差を生んでいると考えられています。つまり、ここまで見てきた出産・育児に伴う離職や、管理職に占める女性割合が低いことが影響していると想定されるのです。
なるほど。女性の就業に関する様々な要因が複雑に絡み合うことで、男女間賃金格差等の問題を引き起こしているのですね。ここまで見てきた問題は、これから解消していかなければならないと思いますが、今後の課題について教えてください。
2.日本の女性雇用の課題
これからの日本の女性雇用には大きく、①女性の労働参加をさらに促すこと、②出産・育児による離職を防ぐことなどが求められます。最初に確認したとおり、女性の労働力率は年々高まっているのですが、実は、有配偶者や子どものいる20~40代女性の労働力率は未婚のそれよりも大きく下回っています。
つまり、家庭や子どもを持つ女性の労働参加が進んでいないということですね。本連載Unit 2で見たような「出産前から働いている女性の約半数が、出産後に退職してしまう」状況を改善し、女性の労働参加をさらに促すにはどのような取り組みが必要になるのでしょうか?
今後の取り組みとして、社会全体で、女性が働き続けられる環境を整えていくことが重要だと考えます。企業だけでなく、行政や自治体、個人・家庭が一体となって「出産・子育て等のライフイベントを受容する環境」を作っていくのです。最後に、皆様へのヒントになればよいと思い、欧州各国と福井県の年齢階級別就業率の比較データを示します。
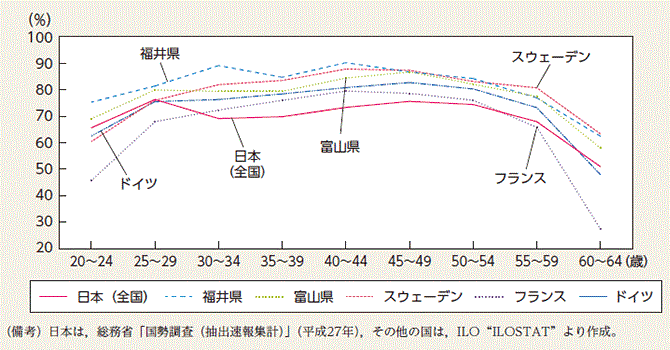
資料:内閣府「男女共同参画白書 平成29年版」
福井県の女性の20代から40代前半にかけての就業率が、OECD加盟国でもトップクラスの水準を誇るスウェーデンの数値を上回っていることを示すデータですね。3世代同居率が高いなど子育て環境が整っていることで、出産後に仕事に復帰しやすい「福井モデル」がうまく機能しているからだと考えられているようですね。
そのとおりです。ただ、核家族世帯の多い東京などの都心では、そっくりとは真似のできないモデルでしょうから、何か別のモデルを模索していかなければなりませんね。いずれにせよ、地域において女性雇用に関する社会的合意が形成されていることが重要である、と言えそうです。
読者の皆様にとっても何かのヒントとなる事例だったと思います。教授、本日はありがとうございました。
※今回の連載内容は、2017年5月9日の講義を参考に執筆しました。
東京労働大学講座「女性労働者の雇用」(永瀬伸子 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授)
※東京労働大学講座は、独立行政法人労働政策研究・研修機構が毎年度開催している、労働問題に関する知識の普及や理解の促進を目的とした講座です。今年度で66回目を数え、これまでの修了者は27,000人を超える歴史と伝統を誇る講座です(2018年1月時点)。
プライムコンサルタントの
コンサルティング
コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?
当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。
これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。
担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。
会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。
人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。



みなさんこんにちは。人事コンサルタント(社会保険労務士・中小企業診断士)の古川賢治です。