転勤・異動時のルール整備

誰もが納得できる転勤・異動のルールを整備する!
コンサルタントが問題点を分析・整理し複数改善策を提案
- 会社名
- K社
- 業種
- 製造・販売業
- 社員数
- 約300名
- 売上高
- 約100億円
概要
核家族化の定着に加え、少子高齢化、価値感の多様化が進む中、働く人々の考え方も次第に変わり、社員が転勤・異動の辞令を簡単には受け入れないケースが増えてきました。ここで紹介するK社は、事業の展開上で不可欠な異動・転勤について、誰もが納得できるルールを構築しようとしている事例です。
背景と課題
K社は、全国の主要都市に営業拠点を持つ計測機器製造販売業です。全国の研究機関や企業の研究所などに対し、代理店を通した販売ルートに強みを持っています。そんなK社ですが、近年、転勤を避けたがる社員が増え、毎年の人事配置に苦慮していました。
営業部門の管理職は、「転勤してこそ営業マンとして育つ、と思っていたが・・・」と嘆きながらも、「子供の教育が、親の介護が・・・」と言われれば、昔のように「個人の事情は知らない。いやなら会社を辞めろ」というマネジメントはできません。その一方で、特定の社員だけがたびたび転勤を求められ、不満が蓄積していくという状況でした。そこでK社は、人事制度全般の整備と合わせ、転勤・異動のルール整備を進めることにしました。
コンサルティングの内容
まず、K社の転勤・異動の運用状況をヒアリングし、これに基づく問題点の分析・整理を行いました。そしてこれを踏まえ、「住宅助成金の見直し」「転勤(発令)時期の見直し」「全国転勤社員と地域限定社員を区分するコース別人事管理」など、いくつかの改善策を提案しました。これを社内プロジェクトで、実現可能性や導入後の影響などの観点から検討してもらいました。
人事配置は経営戦略・組織戦略に付随する事項であるため、人の処遇に主眼を置いたルールにすると、柔軟な配置が阻害されるという問題が生じます。検討は今も継続中で、具体化までには解決すべき事項がまだまだあります。しかし、これまで事業部長の裁量でなんとかやりくりしてきたテーマを、制度化に向けた議論の俎上に載せたことは大きな進展です。私たちも、K社の議論の行方を見守りつつ、企業と個人の調和を実現する新たな枠組みの構築を目指していきます。
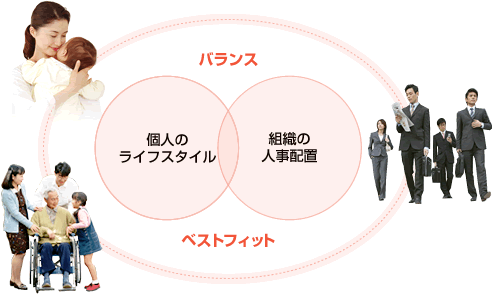
この事例に関するお問合せやコンサルティングのご相談をご希望の方は、以下の「お問合せ」ボタンからお気軽にご連絡ください!



