Unit 8: 派遣労働者の就業実態および活用-駆け出しコンサルタントの学習成長ブログ(人事管理・労働経済編)

前回は、「高齢者雇用を取り巻く現状と動向、今後の課題」について学習しました。
今回は「派遣労働者の就業実態および活用」と題し、派遣労働者の数や就業している業務、労働者派遣の基本的な仕組みについて学習します。また、派遣労働者の活用理由や活用するうえでの問題点、メリット・デメリットについても触れます。働き方が多様化するいま、いわゆる非正規雇用の一部である労働者派遣について一緒に考えていきましょう。
派遣労働者の就業実態
派遣労働者として働く人々
今回は、派遣労働者の就業実態および活用について学習します。突然ですが、派遣労働者として働いている人数はどれくらいか知っていますか?
派遣労働者は全労働者の約2%と言われていますから、およそ100万人ぐらいでしょうか?
総務省が公表した「2017年労働力調査(詳細集計)」によると、役員を除く雇用者5,460万人のうち、労働者派遣事業所の派遣社員として働く人の数は134万人となっています。したがって、全雇用者に占める派遣労働者の比率は、約2.45%です。
個人的にはそれほど多くないという印象ですが、その他の「いわゆる非正規労働者」と比較するとどうなのでしょうか?
2008年のリーマンショックを契機とする「派遣切り」や近年の労働者派遣法の度重なる改正によって、派遣労働という雇用形態は広く知られているところです。ただし、その就業実態となると詳しい人は少ないでしょうから、これを機に基本を押さえておきましょう。まず、いわゆる非正規労働者の数ですが、それについては図表1を見てみましょう。これは、雇用形態別の労働者の割合を示したものです。
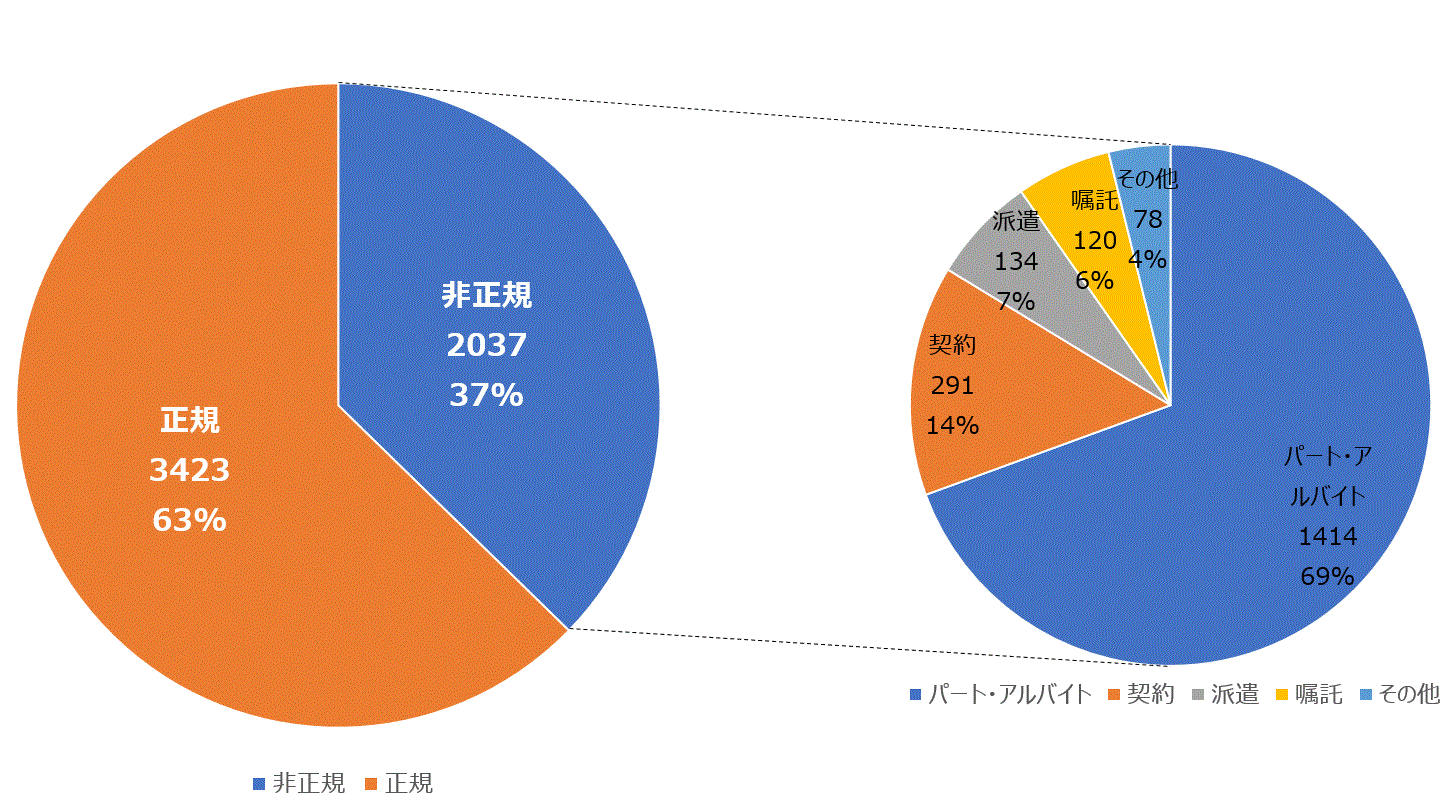
資料:総務省「2017年労働力調査」より作成
これを見ると、非正規労働者全体に占める雇用形態別の割合では、パート・アルバイトが占める割合が69%と大きく、契約社員を加え8割以上を占めているのですね。派遣労働者は非正規労働者全体の中でも約7%の割合なのですね。
はい。「非正規4割時代」と呼ばれる中にあっても、派遣労働者の数自体はそこまで多くないということがお分かりでしょう。次に、派遣労働者が従事している業務について、厚生労働省「2012年派遣労働者実態調査」(図表2)の結果を見ていきましょう。これは、派遣労働者が調査日現在に就いている派遣業務を示したものです。
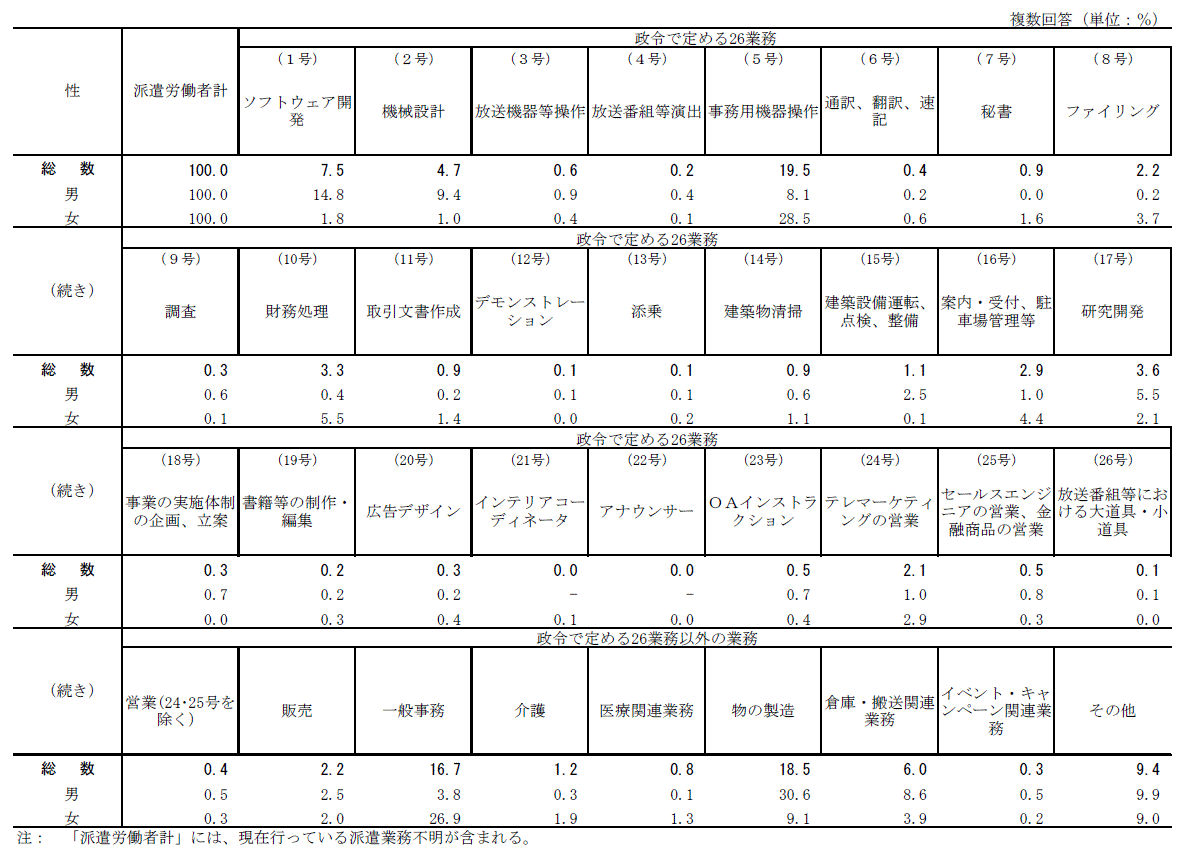
資料:総務省「2012年派遣労働者実態調査」
これを見ると、「事務用機器操作」が19.5%と最も高く、次いで「物の製造」18.5%、「一般事務」16.7%となっているのですね。派遣労働というと、専門的なスキルを持った労働者を外部から獲得するためのものと思っていました。しかしこうして見ると、一般的な事務に従事する人も多く、必ずしも専門的な業務に従事している人ばかりではないということですね。
そうですね。ちなみに、表中の「政令で定める26業務」とは派遣期間に制限がない業務のことですが、この業務区分は労働者派遣法の2015年9月30日改正で撤廃されました。現在は、業務の種類の代わりに、派遣労働者が派遣元で雇用されている期間が有期か無期かによって派遣期間に制限を設けることになっています。
「派遣元」という言葉が出てきましたが、派遣元があるとうことは派遣先もあるということでしょうか。労働者派遣の基本的な仕組みについて教えてください。
労働者派遣の基本的な仕組み
労働者派遣の仕組みは、派遣元・派遣先・労働者の三者で構成されており、雇用関係と指揮命令関係が分離していることが大きな特徴です。具体的には、図表3で見てみましょう。
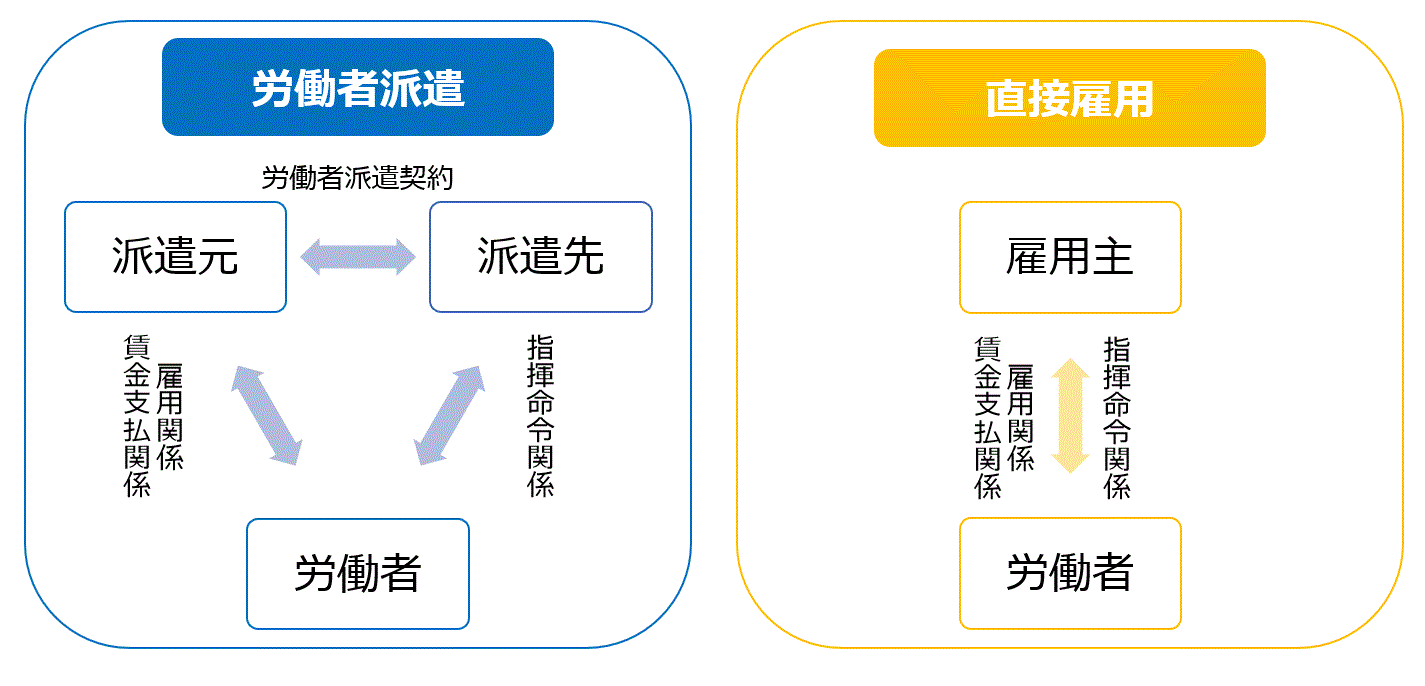
資料:筆者作成
直接雇用(図の右側)では、労働者は雇用関係にある雇用主から指揮命令を受けて業務に従事します。この場合、賃金を支払うのはもちろん雇用主です。一方、労働者派遣(図の左側)では、雇用関係にある雇用主(派遣元)からは直接の指揮命令を受けません。雇われた会社とは別の会社(派遣先)で働くので、派遣先から指揮命令を受けることになります。そして、賃金については雇用主の派遣元が支払います。派遣先は、派遣元との労働者派遣契約によって定めた派遣料金を支払うのみで、派遣労働者に対して賃金を支給する必要はありません。
なるほど。労働者派遣は、派遣元・派遣先・労働者の三位一体で構成される雇用形態なのですね。図表3で比較されている直接雇用と比べて、労働者派遣はより複雑な仕組みとなっていますが、派遣労働者の賃金はどのような状況にあるのでしょうか?
派遣労働者の賃金
それについては次の図表4を見てみましょう。これは、全国および三大都市圏の派遣労働者の時給(1時間あたりの賃金)を示したものです。
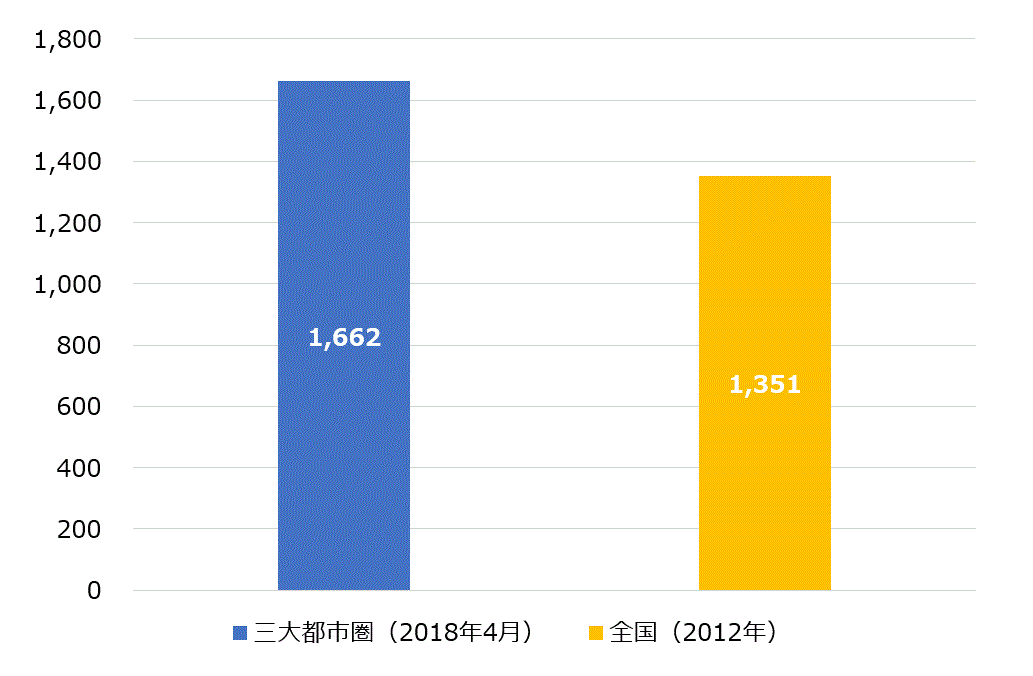
資料:JBRC「派遣スタッフ募集時平均時給調査」および厚生労働省「2012年派遣労働者実態調査」より作成
これを見ると、2018年4月時点では、三大都市圏(関東・東海・関西)の平均時給は1,662円なのですね。
特に最近では、IT業界など人手不足が目立つ業界での派遣時給は上昇傾向にあります。東京などの都市圏では、自動運転向け車載プログラム開発やITシステム開発を担うエンジニア職の募集で、3,000円以上の派遣時給を提示する案件も見られます(2018年6月現在)。
特殊なスキルが求められる専門的な業務ともなると、派遣時給は正社員の時給と同等あるいは上回る水準になるのですね。ところで、企業が派遣労働者を活用する理由にはどのようなものがあるのでしょうか?
派遣労働者の活用
企業が派遣労働者を活用する理由
企業が派遣労働者を活用する理由は様々ですが、主な理由は、次の図表5のとおりです。これは、2010年(平成22年)と2014年(平成26年)の厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」で事業所から得られた回答をもとにしています。
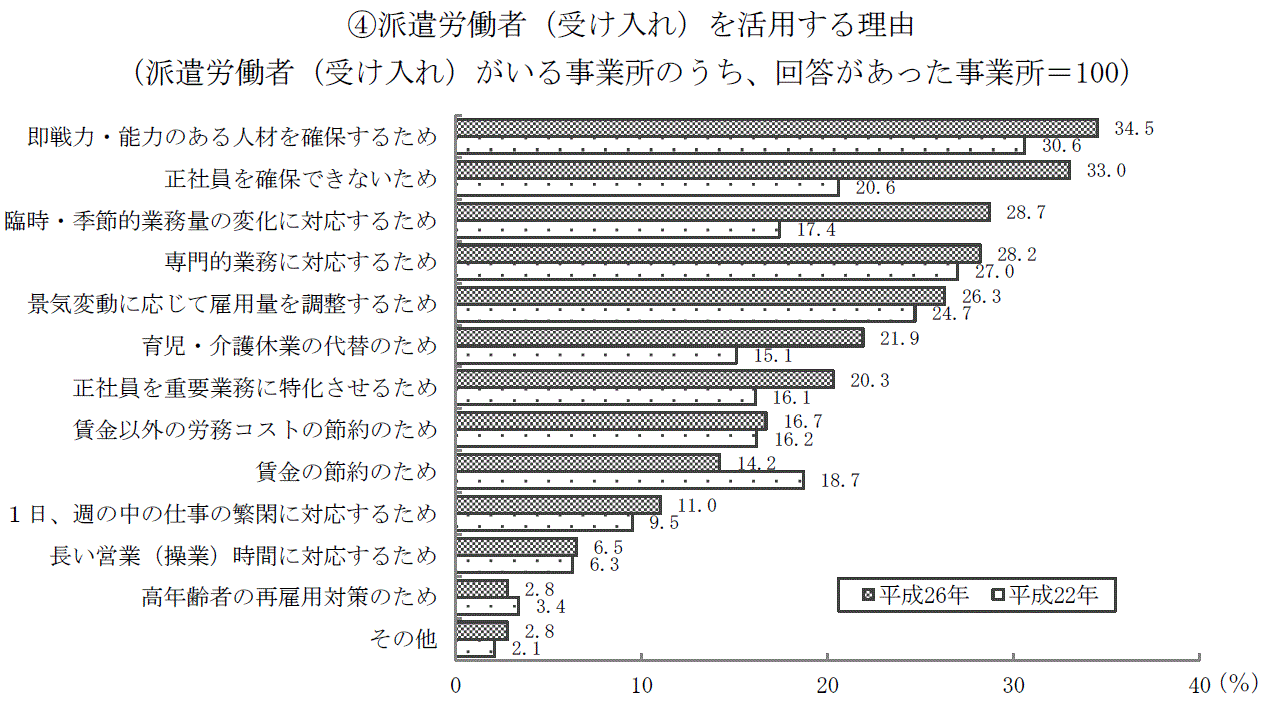
資料:総務省「2012年派遣労働者実態調査」
これを見ると、最も多いのは「即戦力・能力のある人材を確保するため」で、今回(平成26年)が34.5%、前回(平成22年)は30.6%です。第2位は「正社員を確保できないため」33.0%(前回20.6%)です。前回第2位の「専門業務に対応するため」が、今回は4位に順位を下げたようです。ここから、どのようなことが言えるのでしょうか?
企業が派遣労働者を活用する大きな狙いとしては、第一に「即戦力・能力のある人材を確保するため」だと言えるでしょう。また、人手不足を背景に、正社員が確保できない企業が人材確保のために派遣労働者を活用するというニーズも高まっていると言えるでしょう。反対に、パートタイム・契約社員の活用で多く見られる「賃金の節約のため」という理由は、派遣労働者に限ってはそこまで多く見られません。
なるほど、よくわかりました。ところで、企業が派遣労働者の活用を進めるにあたって、問題となる点などは何かありますか?
派遣労働者を活用するうえでの問題点
ここでは詳細なデータは示しませんが、厚生労働省「2014年就業形態の多様化に関する総合実態調査」によると、事業所が派遣労働者を活用するうえで感じている問題点(複数回答)としては、「良質な人材の確保(60.1%)」「仕事に対する責任感(41.4%)」などが挙げられます。
労働者派遣法では派遣先と派遣労働者の事前面接が禁止されているため、派遣先は人材派遣会社(派遣元)からどのような人材が来るのかは分かりません。これが良質な人材の確保を難しくしている一因でもあるのでしょう。ただし、実際の現場では、この事前面接の禁止が守られていないとの声も聞きますが...。
派遣だけでなく、パートタイム・契約社員にも共通して言えることですが、仕事に対する責任感をどのようにして高めていくかが非正規社員をうまく活用するポイントと言えそうですね。最後に、派遣先が派遣労働者を活用するメリット・デメリットを図表6にまとめましたので、確認してください。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
※派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされる制度(2015年10月施行)
専門的な派遣労働者ともなると、新卒で大手企業に入社して定年まで勤めたとしても獲得できないような特殊な専門スキルを保有している人もいます。特に最近では、若年者を中心に人生の価値観や仕事に対する考え方が多様化しており、一つの企業に長年勤めることよりも「専門的な職業能力を身につけプロフェッショナル人材として労働市場を渡り歩いていきたい」と考える人も少なくありません。また、専門スキルを保有した派遣労働者を活用することで、他社に先駆けて事業をスピーディに前進させることも可能です。今後は、雇用形態に関わらず、その人が保有する職業能力をどのようにして活用していくかが、人材戦略において重要となる気がします。教授、本日はありがとうございました。
今回の連載内容は、2017年4月25日の講義を参考に執筆しました。
東京労働大学講座「派遣社員・請負社員の活用」(松浦民恵 法政大学キャリアデザイン学部准教授)
※東京労働大学講座は、独立行政法人労働政策研究・研修機構が毎年度開催している、労働問題に関する知識の普及や理解の促進を目的とした講座です。今年度で66回目を数え、これまでの修了者は27,000人を超える歴史と伝統を誇る講座です(2018年1月時点)。
プライムコンサルタントの
コンサルティング
コンサルティング会社と聞くと、「敷居が高い」「中小企業の当社には関係ない」といった考えをお持ちではありませんか?
当社のクライアントの大半は、従業員数が30~300名ほどの中堅・中小のお客様です。
これらのお客様からは「中小企業の実情を理解したうえで的確なアドバイスをくれる」「話をしっかり受け止めようとしてくれる」「いい意味でコンサル会社っぽくなく、何でも相談できる」といった声を多くいただきます。
担当コンサルタントの「親しみやすさ」も、当社の特長の一つです。
会社の規模に関わらず、一社一社のお客様と親身に対話をすることが当社の基本方針。
人事のご相談はもちろん、それに関連する専門知識を持ったコンサルタントがお客様の悩みをしっかり受け止め、人事にまつわるさまざまな課題を解決に導いてまいります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。



みなさんこんにちは。人事コンサルタント(社会保険労務士・中小企業診断士)の古川賢治です。